↑無料NOTEを書きました。読むと、やる気が出て暗記効率が上がりますから、試験勉強の合間に読むことをオススメします。
1級建築施工管理技術検定試験【二次検定問題】の覚え方と勉強法
このブログは2024年基準の情報をもとに、一級建築施工管理技術検定に出題される可能性がある問題の覚え方や、
法規法令や過去問の重要性を強調し、独自の見解を提供しますが、正確な情報は各公式HP等でご確認ください。
※あくまでも暗記方法は試験対策用の説明として御理解ください。
※二次試験向けの内容です。一次試験の勉強や、復習は↑にあるリンクの、一次試験まとめ一覧がオススメです。
今回のテーマ
【 一次試験復習系の対策[躯体関連] 】
今回のテーマは、一次試験の延長線上にある問題と言える[躯体関連]に関連する問題です。
一次検定50点超えの高得点であれば覚えているかもですが、一次試験まとめ一覧を全て復習しておくことがオススメです。
ここでは、過去に出題された穴埋め問題を基に覚えるポイントを紹介していきます。
【 】内の単語と、赤文字は穴抜きされる可能性がある重要キーワードです。
5つの選択肢から1つの正解を選ぶ五肢択一形式での出題が予想されますので、
一次試験と同じく、ひっかけ用の選択肢には要注意です。
しっかりと正確に暗記しておきましょう。
※あくまでも暗記用ブログですので、正確な情報は各公式ホームページをご確認ください。

【令和6年の過去問を基にしています。】
■出題例として、令和6年では、次の1.から8.の記述において、【 】に当てはまる最も適当な語句又は数値組み合わせを、下の枠内から1つ選びなさい。
という出題形式であり、また更に過去の年度では違う出題形式でしたが、とにかく重要キーワードと数字数値が、
暗記ポイントですから、しっかりと覚えていきましょう。
1. 作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。
通路には、正常の通行を妨げない程度に、【 採光 】又は照明の方法を講じなければならない。
ただし、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。
また、 【 屋内 】に設ける通路は用途に応じた幅を有し、通路面から高さ
【 1.8 】m以内に障害物を置いてはならない。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
あくまでも暗記術としての説明です。
最高の照明じゃないとイヤだと言う、プライド高く、わがままな女優風な作業員を想像します。
私が安全に輝ける最高(採光)の照明じゃないとイヤ(い1、や8→1.8m)※プライド高い。
このフレーズで、採光と高さ1.8mが覚えられます。

2.根切り工事において、掘削底面付近の砂質地盤に上向きの浸透流が生じ、この水の浸透力が砂の水中での
有効重量より大きくなり、砂粒子が水中で浮遊する状態を【 クイックサンド 】という。
【 クイックサンド 】が発生し、沸騰したような状態でその付近の地盤が破壊する現象を【 ボイリング 】という。
また、掘削底面やその直下に難透水層があり、その下にある被圧地下水により掘削底面が持ち上がる現象を
【 盤ぶくれ 】という。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
これは、一次試験の復習なので、覚え方は過去ブログで説明している通りです。
あとは文章からの想像で、浸透流が生じて浮遊している→砂が水中でクイックイッと踊っていると連想して、
クイックサンドと覚え、怒りが湧き上がり全てを破壊(又は崩壊)するボイリング!
という感じで暗記すれば、文章の語句とキーワードが、かんたんに暗記できるはずです。

3.既製コンクリート抗の埋込み工法において、抗心ずれを低減するためには、堀削ロッドの振止め装置を用いることや、
抗心位置から直有二方向に逃げ心を取り、掘削中や抗の建込み時にも逃げ心からの距離を随時確認することが大切である。
一般的な施工精度の管理値は、杭心ずれ量が、D/【 4 】以下(Dは杭直径)、かつ、【 100 】㎜以下、【 鉛直精度 】が1/100以内である。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・施工精度の管理値は、杭心ずれ量が、D/【 4 】以下(Dは杭直径)、かつ、【 100 】㎜以下、【 鉛直精度 】が1/100以内
杭心のずれ、D/4以下がキーワード!
4は、し4、しん、心、芯、杭芯がずれると死ぬほどツライのシ、で4を覚えます。
死なのでダイ、die、死ぬ。
これで簡単にD/4以下を覚えられます。
かつ100ミリ以下は、100%死ぬと覚えます。
あくまでも暗記術ですから、冷静に思い出せば、キーワードから答えが連想できます。
鉛直精度100ミリ以下については、鉛直精度は100点を目指す。という感じです。
100点、ナンバー1、だから、鉛直精度が1/100以内!
そして、そもそも杭で、柱状なので、求められる精度は鉛直だと分かります。
あと、管理値は感覚的に理解しておくことも有効です。
杭のサイズにもよりますが、施工管理値で数ミリや数センチは許容できたとして10センチを超えてずれたら、長さによっては、とんでもないズレになっちゃうよ。だから、10センチ=100ミリ以下って覚えておきましょう。
で、そのズレを防ぐための有効な対応策として。
→直有二方向に逃げ心を取り、掘削中や抗の建込み時にも逃げ心からの距離を随時確認
という流れで覚えます。

4.鉄筋工事において、鉄筋相互のあきは【 粗骨材 】の最大寸法の1.25倍、
【 25 】㎜及び隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍のうち最大のもの以上とする。
鉄筋の間隔は、鉄筋相互のあきに鉄筋の最大外径を加えたものとする。
柱及び梁の主筋のかぶり厚さは、D29以上の異形鉄筋を使用する場合、径(呼び名の数値)【 1.5 】倍以上とする。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
これも一次試験の復習なので、過去ブログで暗記方法を説明した通りです。
D29以上の異径鉄筋でかぶり厚さ1.5倍以上については、以下のフレーズで覚えてください。
にく以上は、かぶりつく、いいこ、
にく以上は、かぶりつく、いちご
肉にかぶりつく、イチゴ異常
この肉異常、おくちなおしに、イチゴに異常にかぶりつく
かぶりついた、で(D)かい肉(29)が異常(以上)で、イチゴ(1.5倍)に異常(以上)にかぶりつく
→柱及び梁の主筋のかぶり厚さは、D29以上の異形鉄筋を使用する場合、径(呼び名の数値)1.5倍以上
これで、きっと瞬間丸暗記!できるはずです!!

5.型枠支保工において、鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、鋼管枠と鋼管枠との間に【 交差筋かい 】を設け、支柱の脚部の滑動を防止するための措置として、支柱の脚部の固定及び【 根がらみ 】の取付け等を行う。
また、パイプサポートを支柱として用いるものにあっては、支柱の高さが
【 3.5 】mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設けなければならない。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
これも一次試験の過去ブログで説明済みですが、この長い文章の覚え方としては、、、
交差する筋交いが根絡みあってサンゴみたいで、フーフー。という感じです。
最後のフーフーは、まるで絡み合うカップルみたいで、ヒューヒューって、昔ながらの感じで、ひやかすとか、熱を冷ますイメージで、フーフー。
とにかく、交差筋違、根絡み、3.5の組み合わせと、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向を覚える。
要注意な、ひっかけ単語は、中桟と布枠と3.0です。
よく読めば絶対に分かるから、丸暗記しておきましょう!

6. コンクリートポンプ工法による1日のコンクリートの打込み区画及び 【 打込み量 】は、建物の規模及び施工時間、レディーミクストコンクリートの供給能力を勘案して定める。
コンクリートの打込み速度は、スランプ18cm程度の場合、打ち込む部位によっても変わるが、20㎥/hから【 30 】㎥/hが目安となる。
また、スランプ10cmから15cmのコンクリートの場合、公称棒径45mmの棒形振動機
1台当あたりの締め能力は、10㎥/hから【 15 】㎥/h程度である。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
この問題は文章から推理していく方法が有効かもしれません。
数字が丸暗記できれば良しですが、文章をそのまま呼んでいけば正解に辿り着けそうな感じです。
まず、供給能力と書いてありますから、打込み量が正解です。順序などではありません。
次に、コンクリートの打込み速度は、スランプ18cm程度の場合、打ち込む部位によっても変わるが、20㎥/hから30㎥/hが目安。
→ここのポイントは、20〜30と、一時間で10㎥くらいの前後は誤差あるよね、という感覚です。
現場で経験があれば、体感しているかもしれません。
一時間、20㎥〜30㎥と、1,2,3を、なんとなく意識して覚えておきましょう。
スランプ10cmから15cmのコンクリートの場合、公称棒径45mmの棒形振動機1台当あたりの締め能力は、10㎥/hから15㎥/h程度
→これも感覚的に分かる人もいるかもですが、締固め能力的に、5㎥程度です。
15㎥が20㎥になることはありませんから要注意!
あくまでも覚え方として説明してくと、
このバイブレーター、いいこだぜ!、いい仕事ができるぜ!いいこ!いいこ!!ヒャッハー!
と、とても絶好調な棒型振動機を手に入れた架空の職人さんを想像します。
いいこで、スランプ10〜15を連想。いい仕事で、1(い)と45(しご)を連想で、棒型振動機1が公称棒径45ミリだと理解し、いいこで、10〜15㎥だと連想します。
ヒャッハーは、なんの意味もないオマケです。
→スランプ10cmから15cmのコンクリートの場合、公称棒径45mmの棒形振動機1台当あたりの締め能力は、10㎥/hから15㎥/h程度
これで丸暗記だぜ!

7.コンクリート工事において、寒中コンクリートでは、レディーミクストコンクリートの荷卸し時のコンクリート温度は、原則として 【 10 】℃以上20℃未満とし、加熱した材料を用いる場合、セメントを投入する直前のミキサ内の骨材及び水の温度は、40°C以下とする。
打込み後のコンクリートは、初期凍害を受けないよう、必要な保温養生を行う。
初期養生の期間は、コンクリートの圧縮強度が【 5 】N/mm2が得られるまでとし、この間は、打ち込んだコンクリートのすべての部分が0°Cを下回らないようにする。
また、【 加熱 】養生中は、コンクリートが乾燥しないように散水等で湿潤養生する。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
この問題は一次試験の復習ではありますが、5とか10とかを確実覚えておかないと、ひっかかるので要注意!
※※あくまでも暗記術です。
荷卸し時のコンクリート温度は、原則として10℃以上20℃未満
→荷卸のときに、ジューってなるのはいいけど、ジュージューって焼き肉みたいな音じゃダメなんだ!
これで、10℃以上20℃未満を覚えます。ジュー×2で20です。
初期養生の期間は、コンクリートの圧縮強度が5N/mm2が得られるまでとし、この間は、打ち込んだコンクリートのすべての部分が0°Cを下回らないようにする。
→寒中なので、凍えないコンクリート、こご(5)えないコンクリートで、5N/mm2を覚える。
凍えないなので、0℃を下回らないようにする。
他の覚え方として、初期養生は所定の強度発生後は解除〜みたいな感じで、ある程度固まった後はやらない。
とか、乾燥収縮後とか、とにかく後、5をキーワードにして覚えるという方法もあります。

8.鉄骨の完全溶込み溶接において、突合せ継手の余盛高さの最小値は【 0 】㎜とする。
裏当て金付きのT継手の余盛高さの最小値は、突き合わせる材の厚さの1/4とし、材の厚さが40㎜を超える場合は【 10 】㎜とする。
裏はつりT継手の余盛高さの最小値は、突き合わせる材の厚さの1/【 8 】とし、材の厚さが40㎜を超える場合は5㎜とする。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
鉄骨の完全溶込み溶接において、突合せ継手の余盛高さの最小値は0㎜
→完全溶け込みなので、0。
8とか10という数字に要注意!ひっかかるな!
裏当て金付きT継手の余盛高さの最小値、突き合わせる材厚さの1/4とし、材の厚さが40㎜を超える場合は10㎜
→あくまでも暗記方法として、裏金問題のTさん、証拠突き合わせる意思あつまる、しおどき。
裏金で、裏当て金付きを連想して、意思で、1/4、しお40、ど→十で10。
裏はつりT継手の余盛高さの最小値は、突き合わせる材の厚さの1/8とし、材の厚さが40㎜を超える場合は5㎜
→あくまでも暗記方法として、裏はつりから、裏口入学や裏口入社的な、方法で人生上手くいったTさんを想像。
事実を突き合わせるのは、イヤ、だから塩対応、ごめん。
イヤで1/8、しお→40、ごめん、5。
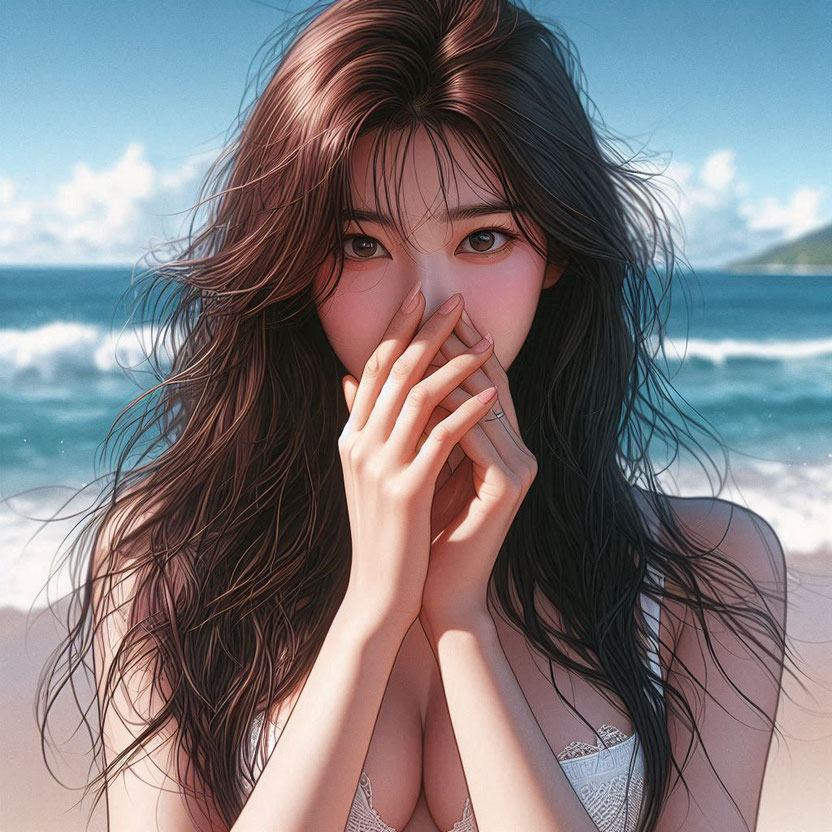
【令和4年の過去問を基にしています。】
1.地盤の平板載荷試験は、地盤の変形及び支持力特性を調べるための試験である。
試験は、直径【 30 】cm以上の円形の板にジャッキにより垂直荷重を与え、載荷圧力、載荷時間、【 沈下量 】を測定する。また、試験結果により求められる支持力特性は、載荷板直径の1.5〜【 2.0 】倍程度の深さの地盤が対象となる。
[覚えるポイントと覚え方]
数字と単語をしっかりと覚えましょう。
特に載荷係数という、ひっかけキーワードには要注意です。
※載荷係数:地盤に載荷試験を行い、圧力Pに対する沈下量Sによる計算式でK値(載荷係数)を求めます。
一般に、このK値が大きいほど、地盤は固く、変形しにくいと言えます。
直径30cm以上の円形の板にジャッキにより垂直荷重を与え、載荷圧力、載荷時間、沈下量を測定
→試験中だから、さわるんじゃねえ。で、さ3わ0、から30センチ以上だと連想して覚えます。
ジャッキにより垂直荷重を与え、載荷圧力、載荷時間、沈下量を測定
→荷重、圧力、時間、そして沈下量を測定。言葉通りの順番だと覚えておきましょう。
支持力特性は、載荷板直径の1.5〜2.0倍程度の深さの地盤が対象
→1.5〜2.0だと、そこまで深くはないと覚えておきましょう。
ただし、この範囲は確実に覚えておきたいので、暗記方法として。
イチゴ煮る。いちご(1.5)、にる(2.0)と覚えてください。
載荷試験、つまり圧力で潰します。
潰すものが、イチゴで、煮たイチゴなら、もうジャム。
載荷、圧力、いちごジャム、イチゴ煮る、1.5〜2.0倍。
これです。
2.根切りにおいて、床付け面を乱さないため、機械式掘削では、通常床付け面上30~50cmの土を残して、残りを手掘りとするか、ショベルの刃を【 平状 】のものに替えて掘削する。
床付け面を乱してしまった場合は、礫や砂質土であれば 、【 転圧 】で締め固め、粘性土の場合は、良質土に置換するか、セメントや石灰等による地盤改良を行う。
また、杭間地盤の掘り過ぎや掻き乱しは、杭の【 水平 】抵抗力に悪影響を与えるので行ってはならない。
[覚えるポイントと覚え方]
これは文章そのままに読めばわかる問題でして、床付面を乱さないことが目標となります。
ひっかけキーワードに要注意で、爪状、水締め、鉛直。
砂質土には転圧。これは一次試験の復習ですから、過去ブログで説明で暗記方法を済みです。
杭の間を掘りすぎれば、そりゃ水平抵抗力に悪影響でしょっていうことで、鉛直は無視しましょう。
3. 場所打ちコンクリート杭地業のオールケーシング工法において、地表面下【 10 】m程度までのケーシングチューブの初期の圧入精度によって以後の掘削の鉛直精度が決定される。
掘削は【 ハンマーグラブ 】を用いて行い、一次スライム処理は、孔内水が多い場合には、【 沈殿バケット 】を用いて処理し、コンクリート打込み直前までに沈殿物が多い場容には、二次スライム処理を行う。
[覚えるポイントと覚え方]
オールケーシング工法、地表面下10m程度までのケーシングチューブの初期の圧入精度によって以後の掘削の鉛直精度が決定
→10mまでが重要、10、10カウント、ボクシング的なスポーツを連想して覚えましょう。
ハンマーグラブを用いて行い、一次スライム処理は、孔内水が多い場合には、沈殿バケットを用いて処理
→ハンマーグラブと沈殿バケットのセットを覚えます。
ハンマーグラブ、ハンマーグローブ、なんだかボクシング的なスポーツが連想できますよね。
ハンマーグラブで、一撃KO、相手は沈殿していくーみたいな連想です。
この2つの連想フレーズを合わせて覚えれば、キーワードと数字が、さくっと丸暗記できますね。
✗ドリリングバケット✗などの、不正解のひっかけキーワードには要注意です。
4. 鉄筋のガス圧接を手動で行う場合、突き合わせた鉄筋の圧接端面間の隙間は 【 2 】mm以下で、偏心、曲がりのないことを確認し、還元炎で圧接端面間の隙間が完全に閉じるまで加圧しながら加熱する。
圧接端面間の隙間が完全に閉じた後、鉄筋の軸方向に適切な圧力を加えながら、 【 中性炎 】により鉄筋の表面と中心部の温度差がなくなるように十分加熱する。
このときの加熱範囲は、圧接面を中心に鉄筋径の【 2 】倍程度とする。
[覚えるポイントと覚え方]
一次試験向けの過去ブログで、還元炎と中性炎の覚え方は説明済みです。
・突き合わせた鉄筋の圧接端面間の隙間は2mm以下で、偏心、曲がりのないことを確認。
・このときの加熱範囲は、圧接面を中心に鉄筋径の2倍程度とする。
あとは、この2つを覚えるだけ。
圧接はダブルピース、圧接成功ダブルピース、圧接大成功!ダブルピース!!
まあ、そんな感じで、2ミリ以下と2倍程度を覚えてください。
二つの鉄筋、一つにするよ、ダブルピース!って感じでお願いします。

5.型枠に作用するコンクリートの側圧に影響する要因として、コンクリートの打込み速さ、比重、打込み高さ及び柱、壁などの部位の影響等があり、打込み速さが速ければコンクリートヘッドが【 大きく 】なって、最大側圧が大となる。
また、せき板材質の透水性文は漏水性が【 大きい 】と最大側圧は小となり、打ち込んだコンクリートと型枠表面との摩擦係数が【 小さい 】ほど、液体圧に近くなり最大側圧は大となる。
[覚えるポイントと覚え方]
この問題は、文章通りですから、ひっかからないように言葉の意味を理解しておきましょう。
一般的に、型枠側圧とは型枠内に流し込まれた硬化前のコンクリートが型枠の側面に加える圧力だと言えます。
・コンクリートヘッドが大きくなると最大側圧が大となる。
→イメージとしては、夏の水遊びで、ホースの直径が大きくなれば、水量が増えて、ビニールプールの側面に高い圧力が掛かる。
・せき板材質の透水性文は漏水性が大きいと最大側圧は小
→水が漏れているなら、抵抗力というか、圧力は少ない。
・打ち込んだコンクリートと型枠表面との摩擦係数が小さいほど、液体圧に近くなり最大側圧は大となる
→例えば、固形物よりも半固形物の方が側圧大で、半固形物よりも液体の方が、側圧が大となる。
摩擦係数が大きいと、それが抵抗となり、側圧が減少するというイメージ。
※とにかくなにがなんでも、型枠表面との摩擦係数が小さいほど、液体圧に近くなり最大側圧は大と覚える。
6.型枠組立てに当たって、締付け時に丸セパレーターのせき板に対する傾きが大きくなると丸セパレーターの
【 破断 】強度が大幅に低下するので、できるだけ垂直に近くなるように取り付ける。
締付け金物は、締付け不足でも締付け過ぎでも不具合が生じるので、適正に使用することが重要である。
締付け金物を締め過ぎると、せき板が【 内側 】に変形する。
締付け金物の締付け過ぎへの対策として、内端太(縦端太)を締付けボルトとできるだけ 【 近接させる 】等の方法がある。
[覚えるポイントと覚え方]
これは、経験があれば、間違えようがない問題と言えるかもですが、ポイントは、破断と、近接させる。
うーん、イメージがしにくい場合には、箱を組み立ててみるとか、ネットで施工画像などを検索するとか、
一度でも見れば分かる問題ですが、ひっかけのキーワードに要注意!圧縮強度とか、離すとか。

7. コンクリート工事において、暑中コンクリートでは、レディーミクストコンクリートの荷卸し時のコンクリート温度は、原則として【 35 】℃以下とし、コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、【 90 】分以内とする。打込み後の養生は、特に水分の急激な発散及び日射による温度上昇を防ぐよう、コンクリート表面への散水により常に湿潤に保つ。
湿潤養生の開始時期は、コンクリート上面ではブリーディング水が消失した時点、せき板に接する面では脱型【 直後 】とする。
[覚えるポイントと覚え方]
これも、一次試験の過去問で学んできた内容だと言えます。
文章終盤の、湿潤養生については、湿潤なので脱型直後という連想はできるはず。
・せき板に接する面では脱型直後とする。
※直前ではない。直前では脱型時にジャマになるし、そもそも湿潤養生されている。という感覚で覚える。
・暑中コンクリートは、荷卸し時の温度は原則35℃以下とし、練混ぜから打込み終了までは、90分以内
→ここは連想でいきます。暑中、暑い、夏、コンクリート温度、体温以下、体温36度より低い、35度以下で。
コンクリートは、体温以下にしてくれ!くれ、9く0れ、90分以内。
夏のコンクリートは体温以下にしてくれ!!!
※内容は、一次試験のおさらいなので、あとは言葉の組み合わせを、確実に覚えるだけです。
8.鉄骨工事におけるスタッド溶接後の仕上がり高さ及び傾きの検査は、【 100 】本又は主要部材1本若しくは1台に溶接した本数のいずれか少ないほうを1ロットとし、1ロットにつき1本行う。
検査する1本をサンプリングする場合、1ロットの中から全体より長いかあるいは短そうなもの、又は傾きの大きそうなものを選択する。
なお、スタッドが傾いている場合の仕上がり高さは、軸の中心でその軸長を測定する。
検査の合否の判定は限界許容差により、スタッド溶接後の仕上がり高さは指定された寸法の±【 2 】㎜以内、かつ、スタッド溶接後の傾きは【 5 】度以内を適合とし、検査したスタッドが適合の場合は、そのロットを合格とする。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・スタッド溶接後の仕上がり高さ及び傾きの検査は100本又は、主要部材1本若しくは、1台に溶接した本数のいずれか少ないほうを1ロットとし、1ロットにつき1本行う
→あくまでも覚え方ですが、スタッドは、数字の1っぽいので、関連する数字は1が多いと覚える。
ポイントは100本ですが、検査なので100点を目指す、1番いい品質を目指す。という感じで100と1を覚えます。

【令和2年の過去問を基にしています。】
1.つり足場における作業床の最大積載荷重は、現場の作業条件等により定めて、これを超えて使用してはならない。
つり足場のつり材は、ゴンドラのつり足場を除き、定めた作業床の最大積報荷重に対して、使用材料の種類による安全係数を考慮する必要がある。
安全係数は、つりワイヤロープおよびつり鋼線は【 10 】以上、つり鎖およびつりフックは【 5.0 】以上、つり鋼帯及びつり足場の上下支点部は鋼材の場合【 2.5 】以上とする。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
安全係数は、つりワイヤロープおよびつり鋼線は10以上、つり鎖およびつりフックは5.0以上、つり鋼帯及びつり足場の上下支点部は鋼材の場合2.5以上
・つりワイヤロープおよびつり鋼線は10以上
→特に人命がかかっていますから、ひとの命、ひと(と、十、10)、または十分な安全係数で、10を丸暗記。
・つり鎖およびつりフックは5.0以上
→鎖やフックは、強い合金で出来ていますから、合金で、ごうきん、ご(5)。
つり鋼帯及びつり足場の上下支点部は鋼材の場合2.5以上
→ニコニコ作業ができる安全性が必要です。ということで、にこ、2,5、2.5.。
2.地下水処理における排水工法は、地下水の揚水によって水位を必要な位置まで低下させる工法であり、
地下水位の低下量は揚水量や地盤の【 透水性 】によって決まる。
必要場水量が非常に【 多い 】場合、対象とする帯水層が深い場合や帯水層が砂層である場合に
【 ディープウェル 】工法が採用される。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
これも一次試験でよく出る過去問の内容です。
過去ブログで説明済みですが、ディープウェルとウェルポイントの違いは、確実に理解しておきましょう。
※ウェルポイントは、ディープウェルよりも揚水量は少なく、かつ帯水層が低い場合に有効で、一般に対応できる深さは5〜6m迄程度ですが、広範囲で施工可能という特徴があります。
3.既製コンクリートの埋込み工法において、杭心ずれを低減するためには、掘削ロッドの振れ止め装置を用いることや、杭心位置から直角二方向に逃げ心を取り、掘削中や杭の建込み時にも逃げ心からの距離を随時確認することが大切である。
一般的な施工精度の管理値は、杭心ずれ量が【 D/4 】以下(Dは杭直径)、かつ、【 100 】㎜以下、傾斜【 1/100 】以内である。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
令和6年と、ほとんど同じです。
・施工精度の管理値は、杭心ずれ量が、D/【 4 】以下(Dは杭直径)、かつ、【 100 】㎜以下、【 鉛直精度(傾斜) 】が1/100以内
杭心のずれ、D/4以下がキーワード!
4は、し4、しん、心、芯、杭芯がずれると死ぬほどツライのシ、で4を覚えます。
死なのでダイ、die、死ぬ。
これで簡単にD/4以下を覚えられます。
かつ100ミリ以下は、100%死ぬと覚えます。
あくまでも暗記術ですから、冷静に思い出せば、キーワードから答えが連想できます。
鉛直精度100ミリ以下については、鉛直精度は100点を目指す。という感じです。
100点、ナンバー1、だから、鉛直精度(傾斜)が1/100以内!
そして、そもそも杭で、柱状なので、求められる精度は鉛直だと分かります。
あと、管理値は感覚的に理解しておくことも有効です。
杭のサイズにもよりますが、施工管理値で数ミリや数センチは許容できたとして10センチを超えてずれたら、長さによっては、とんでもないズレになっちゃうよ。だから、10センチ=100ミリ以下って覚えておきましょう。
で、そのズレを防ぐための有効な対応策として。
→直有二方向に逃げ心を取り、掘削中や抗の建込み時にも逃げ心からの距離を随時確認
という流れで覚えます。

4.鉄筋工事において、鉄筋相互のあきは粗骨材の最大寸法の1.25倍、【 25 】㎜及び降り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均値の【 1.5 】倍のうち最大のもの以上とする。
鉄筋の間隔は鉄筋相互のあきに鉄筋の最大外径を加えたものとする。
柱及び梁の主筋のかぶり厚さはD29以上の異形鉄筋を使用する場合は径(呼び名の数値)の【 1.5 】倍以上とする。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
一次試験の過去ブログで、暗記方法は説明済みの内容です。
あとは、言葉の組み合わせですが、手動、なので、人の手、人、有資格者、有資格という連想で手動=有資格。
あとの資格種類ごとの作業可能範囲は過去ブログを御覧ください。
5.型枠工事における型枠支保工で、鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、鋼管枠と鋼管枠との間に
【 交差筋かい 】を設け、支柱の脚部の滑動を防止するための措置として、支柱の脚部の固定および
【 根がらみ 】の取付けなどを行う。
また、パイプサポートを支柱として用いるものにあっては、支柱の高さが3.5mを超えるときは、高さ2m以内ごとに【 水平つなぎ 】を2方向に設けなければならない。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
※令和6年と同じです。
これも一次試験の過去ブログで説明済みですが、この長い文章の覚え方としては、、、
交差する筋交いが根絡みあってサンゴみたいで、フーフー。という感じです。
最後のフーフーは、まるで絡み合うカップルみたいで、ひやかすとか、熱を冷ますイメージで、フーフー。
とにかく、交差筋違、根絡み、3.5の組み合わせと、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向を覚える。
要注意な、ひっかけ単語は、中桟と布枠と3.0です。
よく読めば絶対に分かるから、丸暗記しておきましょう!
6.型枠の高さが【 4.5 】m以上の柱にコンクリートを打ち込む場合、たて形シュートや打込み用ホースを接続してコンクリートの分離を防止する。
たて形シュートを用いる場合、その投入口と排出口との水平方向の距離は、垂直方向の高さの約【 1/2 】以下とする。
また、斜めシュートはコンクリートが分離しやすいが、やむを得ず斜めシュートを使用する場合で、シュートの排出口に漏斗管を設けない場合は、その傾斜角度を水平に対して【 30 】度以上とする。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・コンクリートの分離防止、型枠高さ4.5m以上、たて形シュート投入口と排出口との水平方向の距離は垂直方向の高さの約1/2以下。
→あくまでも暗記術です。コンクリートの分離防止っていうのは、いい仕事っていうものを教えてくれる。
コンクリートと同じで、仕事とプライベートも、いい意味で分離しちゃいけないんだぜ。
高い場所でも、いい仕事をするためには、仕事は約1/2以下で、あとはプライベートも充実させなきゃって感じで。
しごと、し4、ご5、型枠高さ4.5m以上。あと約1/2以下も、この組み合わせで覚えます。
・やむを得ず斜めシュートを使用する場合で、シュートの排出口に漏斗管を設けない場合は、その傾斜角度を水平に対して30 度以上。
→とにかく30度を覚えればいいので。暗記術として。
シュートの排出口に漏斗管を設けないで、その傾斜角度を水平に対して30 度以上。に、できないヤツはサレ!
プライベートがなんだとか、ゴチャゴチャ言っているヤツはサレ!
シュートで流してやる!サレ!で、サ3レ0で、30度を覚えます。

7.溶融亜鉛めっき高力ボルト接合に用いる溶融亜鉛めっき高力ボルトは、建築基準法に基づき認定を受けたもので、セットの種類は1種、ボルトの機械的性質による等級は【 F8T 】が用いられる。
溶融亜鉛めっきを施した鋼材の摩擦面の処理は、すべり係数が0.4以上確保できるブラスト処理又は
【 りん酸塩 】処理とし、H形鋼ウェブ接合部のウェブに処理を施す範囲は、添え板が接する部分の添え板の外周から5㎜程度【 内側 】とする。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・一般的に F8Tとは、 F8T(エフハチティ)ボルトで、引張強度が800N〜1000N/mm²以上の高力ボルト(ハイテンボルト)の等級の一つで、溶融亜鉛めっき(ドブ漬けめっき)が施された六角ハイテンションボルト。
※覚え方としては、大阪弁風でいきます。
普通やで、このハイテンション。ふFつう、や8で、このハイテTンション。で覚えます。
・すべり係数が0.4以上確保できるブラスト処理又はりん酸塩処理。この部分は一次試験のおさらいです。
ここでは、内側か外側かをおさえておきましょう!
ここは勿論、内側が正解!イメージとしては無駄に外部を処理しない。というイメージと、
外側には5㎜も余裕がないケースがある。とか、そんなイメージで、内側だと確実に覚えます。
8.鉄骨の現場溶接作業において、防風対策は特に配慮しなければならない事項である。
アーク熱によって溶かされた溶融金属は大気中の酸素や【 窒素 】が混入しやすく、凝固するまで適切な方法で外気から遮断する必要があり、
このとき遮断材料として作用するものが、ガスシールドアーク溶接の場合は【 シールドガス 】である。
しかし、風の影響により【 シールドガス 】に乱れが生じると、溶融金属の保護が不完全になり溶融金属内部に【 ブローホール 】が生じてしまう。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
ここでは、溶接の代表的な不具合症状であるアンダーカットとブローホールの明確化がポイントです。
ブローホールとは、溶接金属の中にできる気泡や、空洞のこと。
今回の文章では、風というキーワードがありますから、風、ブロー、ブローホールだと、しっかり覚えましょう。
では、アンダーカットとは?
溶接部の母材側が削られ、溝状にえぐれてしまう不具合。
溶接ビードの端部にできる“くぼみ”で、強度低下や応力集中の原因になります。
窒素、シールドガスは文章をよく読めば、違和感なく理解できるはずですが、
詳しい溶接の仕組みなどは、ネットや、参考書で確認しておくことがオススメです。
一度、理解さえしてしまえば、問題文章を読めば分かるラッキー問題だと言えます。

【平成30年の過去問を基にしています。】
1.平板載荷試験は、地盤の変形や強さなどの支持力特性を直接把握するために実施される。
試験地盤に礫が混入する場合には、礫の最大直径が載荷板直径の【 1/5 】程度を目安とし、この条件を満たさない場合は大型の載荷板を用いることが望ましい。
試験地盤は、半無限の表面を持つと見なせるよう載荷板の中心から載荷板直径の【 3 】倍以上の範囲を水平に整地する。
また、計画最大荷重の値は、試験の目的が設計荷重を確認することにある場合は、長期設計荷重の【 3 】倍以上に設定する必要がある。
[覚えるポイントと覚え方]
・礫の最大直径が載荷板直径の1/5 程度を目安とし、この条件を満たさない場合は大型の載荷板を用いること
→いい小石(いーこ1/5、石=礫)と思えないレベルの大きさの石があったら、大型の載荷板を用いる。と丸暗記。
・試験地盤は、半無限の表面を持つと見なせるよう載荷板の中心から載荷板直径の3倍以上の範囲を水平に整地する。
→半無限と見(み、3)えるように、3倍以上の範囲を水平に整地する。
計画最大荷重の値は、試験の目的が設計荷重を確認することにある場合は、長期設計荷重の3倍以上に設定する必要
→最(さ3い)大荷重値で、3倍以上だと覚える。
2.根切り工事において、掘削底面付近の砂質地盤に上向きの浸透流が生じ、この水の浸透力が砂の水中での有効重量より大きくなり、
砂粒子が水中で浮遊する状態を【 クイックサンド 】という。
【 クイックサンド 】が発生し、沸騰したような状態でその付近の地盤が崩壊する現象を【 ボイリング 】という。
また、掘削底面やその直下に難透水層があり、その下にある被圧地下水により掘削底面が持ち上がる現象を【 盤ぶくれ 】という。
[覚えるポイントと覚え方]
令和6年と同じです。
崩壊か破壊かという違いはありますが、よくでる過去問ほど確実かつ正確に暗記しましょう!
これは、一次試験の復習なので、覚え方は過去ブログで説明している通りです。
あとは文章からの想像で、浸透流が生じて浮遊している→砂が水中でクイックイッと踊っていると連想して、
クイックサンドと覚え、怒りが湧き上がり全てを破壊(又は崩壊)するボイリング!
という感じで暗記すれば、文章の語句とキーワードが、かんたんに暗記できるはずです。
3.場所打ちコンクリート地業のオールケーシング工法における掘削は、【 ケーシングチューブ 】を搖動(揺動)または回転圧入し、土砂の崩壊を防ぎながら、【 ハンマーグラブ 】により掘削する。
常水面以下に細かい砂層が5m以上ある場合は、 【 ケーシングチューブ 】の外面を伝って下方に流れる水の浸透流や搖動(揺動)による振動によって、周囲の【 砂 】が締め固められ【 ケーシングチューブ 】が動かなくなることがあるので注意する。
支持層の確認は、【 ハンマーグラブ 】でつかみ上げた土砂を土質柱状図及び土質資料と対比して行う。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
現場経験があれば、わかりやすい問題かもしれません。
オールケーシング工法なので、ケーシングチューブが正解です。
不正解は、表層ケーシング。
※尚、ケーシングチューブが大きな鋼管だとイメージできない場合は、ネットで検索してみることがオススメです。
4.ガス圧接の技量資格種別において、【 手動 】ガス圧接については、1種から4種まであり、2種、3種、4種となるに従って、圧接作業可能な鉄筋径の範囲が【 大きく 】なる。
技量資格種別が1種の圧接作業可能範囲は、異形鉄筋の場合は呼び名D【 25 】以下である。
[覚えるポイントと覚え方]
令和4年と同じです。
一次試験の過去ブログで暗記方法は説明済みの内容です。
あとは、言葉の組み合わせですが、手動、なので、人の手、人、有資格者、有資格という連想で手動=有資格。
あとの資格種類ごとの作業可能範囲は過去ブログを御覧ください。
5.鉄筋のガス圧接継手の継手部の外観検査において、不合格となった圧接部の処置は次による。
圧接部のふくらみの直径や長さが規定値に満たない場合は、再加熱し、【 加圧 】して所定のふくらみに修正する。
圧接部の折曲がりの角度が【 2 】度以上の場合は、再加熱して修正する。
圧接部における鉄筋中心軸の【 偏心量 】が規定値を超えた場合は、圧接部を切り取って再圧接する。
[覚えるポイントと覚え方]
これも一次試験のおさらいですから、過去ブログの再確認がオススメです。
あとは、言葉の組み合わせを覚えておきましょう。
再加熱なので、加圧が正解です。徐冷などのひっかけに要注意!
・圧接部の折曲がりの角度が2度以上の場合は、再加熱して修正する。
→再加熱で二度目なので、二度、2度。と覚えましょう。
6.型枠組立てに当たって、締付け時に丸セパレーターのせき板に対する傾きが大きくなると丸セパレーターの破断強度が大幅に低下するので、できるだけ【 直角 】に近くなるように取り付ける。
締付け金物は、締付け不足でも締付けすぎても不具合が生じるので、適正に使用することが重要である。締付け金物を締付けすぎると、せき板が【 内側 】に変形する。締付け金物の締付けすぎへの対策として、内端太(縦端太)を締付けボルトとできるだけ【 近接させる or 近づける 】等の方法がある。
[覚えるポイントと覚え方]
令和6年と、ほぼ同じ問題です。
これは、経験があれば、間違えようがない問題と言えるかもですが、ポイントは、破断と、近接させる。
うーん、イメージがしにくい場合には、箱を組み立ててみるとか、ネットで施工画像などを検索するとか、
一度でも見れば分かる問題ですが、ひっかけのキーワードに要注意!圧縮強度とか、離すとか。
補足としては、直角にすること。斜めになることで破断の可能性が高くなりますから、直角が正解です。
7.コンクリートポンプ工法による1日におけるコンクリートの打込み区画及び【 打込み量 】は、建物の規模及び施工時間、レディーミクストコンクリートの供給能力を勘案して定める。
コンクリートの打込み速度は、スランプ18cm程度の場合、打込む部位によっても変わるが、20~【 30 】㎥/hが目安となる。また、スランプ10~15cmのコンクリートの場合、公称棒径45mmの形振動機台当たりの締固め能力は、 10~【 15 】㎥/h程度である。
なお、コンクリートポンプ台当たりの圧送能力は、20~50㎥/hである。
[覚えるポイントと覚え方]
これも令和6年と、ほぼ同じ。出題回数が多い過去問ほど、しっかりと覚えておきましょう。
この問題は文章から推理していく方法が有効かもしれません。
数字が丸暗記できれば良しですが、文章をそのまま呼んでいけば正解に辿り着けそうな感じです。
まず、供給能力と書いてありますから、打込み量が正解です。順序などではありません。
次に、コンクリートの打込み速度は、スランプ18cm程度の場合、打ち込む部位によっても変わるが、20㎥/hから30㎥/hが目安。
→ここのポイントは、20〜30と、一時間で10㎥くらいの前後は誤差あるよね、という感覚です。
現場で経験があれば、体感しているかもしれません。
一時間、20㎥〜30㎥と、1,2,3を、なんとなく意識して覚えておきましょう。
スランプ10cmから15cmのコンクリートの場合、公称棒径45mmの棒形振動機1台当あたりの締め能力は、10㎥/hから15㎥/h程度
→これも感覚的に分かる人もいるかもですが、締固め能力的に、5㎥程度です。
15㎥が20㎥になることはありませんから要注意!
あくまでも覚え方として説明してくと、
このバイブレーター、いいこだぜ!、いい仕事ができるぜ!いいこ!いいこ!!ヒャッハー!
と、とても絶好調な棒型振動機を手に入れた架空の職人さんを想像します。
いいこで、スランプ10〜15を連想。いい仕事で、1(い)と45(しご)を連想で、棒型振動機1が公称棒径45ミリだと理解し、いいこで、10〜15㎥だと連想します。
ヒャッハーは、なんの意味もないオマケです。
→スランプ10cmから15cmのコンクリートの場合、公称棒径45mmの棒形振動機1台当あたりの締め能力は、10㎥/hから15㎥/h程度
これで丸暗記だぜ!
8.鉄骨工事におけるスタッド溶接後の仕上がり高さ及び傾きの検査は、【 100 】本または主要部材1本もしくは1台に溶接した本数のいずれか少ないほうを1ロットとし、1ロットにつき【 1 】本行う。
検査する【 1 】本をサンプリングする場合、1ロットの中から全体より長いかあるいは短そうなもの、または傾きの大きそうなものを選択する。
なお、スタッドが傾いている場合の仕上がり高さは、軸の中心でその軸長を測定する。検査の合否の判定は限界許容差により、スタッド溶接後の仕上がり高さは指定された寸法の±2mm以内、かつ、スタッド溶接後の傾きは【 5 】以内を適合とし、検査したスタッドが適合の場合は、そのロットを合格とする。
[覚えるポイントと覚え方]
これは、令和4年と、ほぼ同じです。
・スタッド溶接後の仕上がり高さ及び傾きの検査は100本又は、主要部材1本若しくは、1台に溶接した本数のいずれか少ないほうを1ロットとし、1ロットにつき1本行う
→あくまでも覚え方ですが、スタッドは、数字の1っぽいので、関連する数字は1が多いと覚える。
ポイントは100本ですが、検査なので100点を目指す、1番いい品質を目指す。という感じで100と1を覚えます。
補足ですが、スタッドの傾きなどは1次試験のおさらいですので、過去ブログの確認がオススメです。
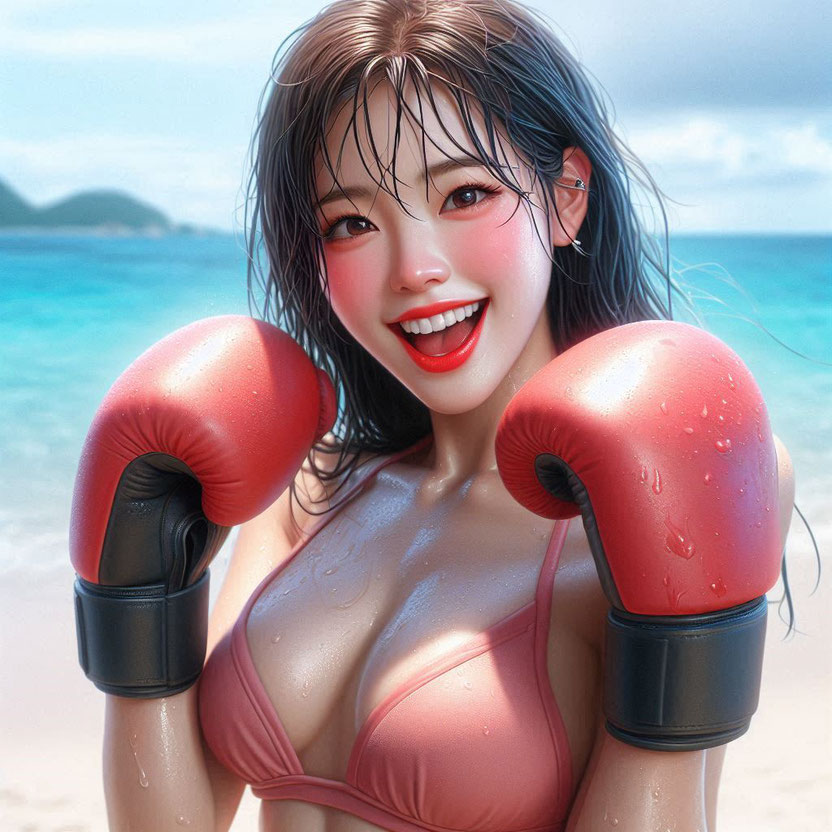

【平成30年②の過去問を基にしています。】
1.地盤の平板載荷試験は、地盤の変形や強さなどの支持力特性を調べるための試験である。
試験は、直径【 30 】㎝以上の円形の鋼板に【 油圧ジャッキ 】により垂直荷重を与え、載荷圧力、載荷時間、沈下量を測定する。
また、試験結果より求まる支持力特性は、載荷板直径の1.5~【 2.0 】倍程度の深さの地盤が対象となる。
[覚えるポイントと覚え方]
これも令和4年に出題と同じ!
数字と単語をしっかりと覚えましょう。
特に載荷係数という、ひっかけキーワードには要注意です。
※載荷係数:地盤に載荷試験を行い、圧力Pに対する沈下量Sによる計算式でK値(載荷係数)を求めます。
一般に、このK値が大きいほど、地盤は固く、変形しにくいと言えます。
直径30cm以上の円形の板にジャッキにより垂直荷重を与え、載荷圧力、載荷時間、沈下量を測定
→試験中だから、さわるんじゃねえ。で、さ3わ0、から30センチ以上だと連想して覚えます。
ジャッキにより垂直荷重を与え、載荷圧力、載荷時間、沈下量を測定
→荷重、圧力、時間、そして沈下量を測定。言葉通りの順番だと覚えておきましょう。
支持力特性は、載荷板直径の1.5〜2.0倍程度の深さの地盤が対象
→1.5〜2.0だと、そこまで深くはないと覚えておきましょう。
ただし、この範囲は確実に覚えておきたいので、暗記方法として。
イチゴ煮る。いちご(1.5)、にる(2.0)と覚えてください。
載荷試験、つまり圧力で潰します。
潰すものが、イチゴで、煮たイチゴなら、もうジャム。
載荷、圧力、いちごジャム、イチゴ煮る、1.5〜2.0倍。
これです。
2.山留め工事における切梁を鉛直方向に対して斜めに取り付けた斜め切梁においては、切梁軸力の【 鉛直分力 】が作用するため、山留め壁側の腹起しの受けブラケットに加え、押さえブラケットを取り付け、反対側は十分な剛性を有する控え杭や駆体で受ける。
また、腹起しにはスチフナー補強を行い、ウェブの局部【 座屈 】やフランジの曲がりを防止する。
控え抗で受ける場合は、プレロードの導入により控え杭に荷重を与え、根切り後の【 変位量 】を低減させる。ただし、軟弱地盤では控え杭の【 変位量 】が大きくなるため、駆体で受けるようにする。
[覚えるポイントと覚え方]
・鉛直分力
極端な例として、少し重たい袋をイメージする。買い物でもゴミでもいい。
袋を真上に持ち上げる → 力は全て鉛直分力、袋はまっすぐ上がるため、持ち上げやすい。
袋を斜めに持ち上げる → 一部の力が横方向に逃げて、鉛直分力が減るため、同じ重さでも重く感じる。
・プレロードがどういう物か知っていれば、変位量に気付ける。
イメージできない人は、ネットや参考書などで調べてみよう。
・ここでの1番のポイントは、
腹起しにはスチフナー補強を行い、ウェブの局部座屈やフランジの曲がりを防止
フランジの曲がりなので、局部座屈という連想で、破断とかの選択肢にひっかからないように注意!
あくまでも暗記術として、局部→蹴られる→痛い→座屈する。
これで覚えるという方法もあります。
3.場所打ちコンクリート杭地業のオールケーシング工法において、地表面下10m程度までのケーシングチューブの初期の圧入精度によって以後の掘削の鉛直精度が決定される。
掘削は【 ハンマーグラブ 】を用いて行い、1次スライム処理は、孔内水が【 多い 】場合には、【 沈殿パケット 】を用いて処理を行う。また、沈殿物が多い場合には、コンクリート打込み直前までに、2次スライム処理を行う。
[覚えるポイントと覚え方]
これも令和4年と同じ内容です。
オールケーシング工法、地表面下10m程度までのケーシングチューブの初期の圧入精度によって以後の掘削の鉛直精度が決定
→10mまでが重要、10、10カウント、ボクシング的なスポーツを連想して覚えましょう。
ハンマーグラブを用いて行い、一次スライム処理は、孔内水が多い場合には、沈殿バケットを用いて処理
→ハンマーグラブと沈殿バケットのセットを覚えます。
ハンマーグラブ、ハンマーグローブ、なんだかボクシング的なスポーツが連想できますよね。
ハンマーグラブで、一撃KO、相手は沈殿していくーみたいな連想です。
この2つの連想フレーズを合わせて覚えれば、キーワードと数字が、さくっと丸暗記できますね。
4.鉄筋の機械式継手において、カップラー等の接合部分の耐力は、継手を設ける主筋等の降伏点に基づく耐力以上とし、引張力の最も小さな位置に設けられない場合は、当該耐力の【 1.35 】倍以上の耐力または主筋等の引張強さに基づく耐力以上とする。
モルタル、グラウト材その他これに類するものを用いて接合部を固定する場合にあっては、当該材料の強度を【 50 】N/mm2以上とする。
ナットを用いた【 トルク 】 の導入によって接合部を固定する場合にあっては、所定の数値以上の
【 トルク 】値とし、導入軸力は30N/mm2を下回ってはならない。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
※過去問では、正解のトルクが曲げモーメントという、ひっかけキーワードに置き換えられていました。
・カップラーと1.35倍以上の組み合わせは、カップラーメンは、1分、3分、5分の3種類が多いと覚えます。
・接合部を固定する、50N/mm2以上の覚え方は、接合部は強くする、接合は剛、つよし、剛、50を剛(ごう)!
・ナット→トルク、しりとりで覚えます。30N/mm2を下回ってはならない→よくみる(み3、る0)で覚える。
5.鉄筋のガス圧接を手動で行う場合、突き合わせた鉄筋の圧接端面間のすき間は【 2 】mm以下で、
偏心、曲がりのないことを確認し、還元炎で圧接端面間のすき間が完全に閉じるまで加圧しながら加熱する。
圧接面間のすき間が完全に閉じた後、鉄筋の軸方向に適切な圧力を加えながら、【 中性炎 】により鉄筋の表面と中心部の温度差がなくなるように十分加熱する。
このときの加熱範囲は、圧接面を中心に鉄筋径の【 2 】倍程度とする。
[覚えるポイントと覚え方]
令和4年と同じ問題です。
一次試験向けの過去ブログで、還元炎と中性炎の覚え方は説明済みです。
・突き合わせた鉄筋の圧接端面間の隙間は2mm以下で、偏心、曲がりのないことを確認。
・このときの加熱範囲は、圧接面を中心に鉄筋径の2倍程度とする。
あとは、この2つを覚えるだけ。
圧接はダブルピース、圧接成功ダブルピース、圧接大成功!ダブルピース!!
まあ、そんな感じで、2ミリ以下と2倍程度を覚えてください。
6.型枠の構造計算に用いる積載荷重は、労働安全衛生規則に、「設計荷重として、型枠支保工が支えている物の重量に相当する荷重に、型枠1㎡につき【 150 】kg 以上の荷重を加えた荷重」と定められている。
通常のポンプ工法による場合、打込み時の積載荷重は【 1.5 】kN/㎡とする。
打込みに一輪車を用いる場合、作業員、施工機械、コンクリート運搬車及びそれらの衝撃を含めて、積載荷重は【 2.5 】kN/㎡を目安とする。
[覚えるポイントと覚え方]
・型枠の構造計算に用いる積載荷重は、型枠1㎡につき150 kg 以上の荷重を加えた荷重
・通常のポンプ工法による場合、打込み時の積載荷重は1.5kN/㎡とする。
・打込みに一輪車を用いる場合、作業員、施工機械、生コン運搬車及びそれらの衝撃を含め、積載荷重は2.5kN/㎡を目安とする。
これは、暗記フレーズで乗り切りましょう。
型枠計算中に、ふと思う。型枠って、いいゴール、ポンプでイチゴ打ち込む、ニコニコな衝撃。
これは、型枠の構造計算をして疲れて妄想をしているイメージです。
ふと思う、おもう、重う、荷重。いいゴール、いーごーる、1い5ご0る。
で、型枠1㎡につき150 kg 以上の荷重を加えた荷重
イチゴ、1.5。
ニコニコ、2.5。
さあ、これで覚えましょう。
7.コンクリートポンプを用いてコンクリートを打ち込む際、コンクリートポンプ1台当たりの1日の打込み量の上限は【 250 】㎥を目安とし、輸送管の大きさは圧送距離、圧送高さ、コンクリートの圧送による品質への影響の程度などを考慮して決める。
輸送管の径が大きいほど圧力損失が 【 小さく 】なる。
コンクリートの圧送に先立ちポンプ及び輸送管の内面の潤滑性の保持のため、水及び【 モルタル 】を圧送する。
[覚えるポイントと覚え方]
この問題では、よく読めば、小さくなる。と、モルタル。は分かるはずです。
あとは、250㎥を覚えるだけ。
あくまでも暗記術です。
いいから、頑張れ!心がにごるまで!で覚えます。
い(1、1日)い(1台)から、頑張れ!心が、に(2)ご(5)る(0)
1日の上限は、心がにごるまで!やる気と疲労感で、にごるまで!に2ご5る0。
→コンクリートポンプ1台当たりの1日の打込み量の上限は250㎥を目安
8.鉄骨の完全溶込み溶接において、完全溶込み溶接突合せ継手及び角継手の余盛高さの最小値は【 0 】㎜とする。
裏当て金付きのT継手の余盛高さの最小値は、突き合わせる材の厚さの1/4とし、材の厚さが40㎜を超える場合は【 10 】㎜とする。
裏はつりT継手の余盛高さの最小値は、突き合わせる材の厚さの【 1/8 】 とし、材の厚さが40㎜を超える場合は5㎜とする。
余盛は応力集中を避けるため、滑らかに仕上げ、過大であったり、ビード表面に不整があってはならない。
[覚えるポイントと覚え方]
令和6年の問題と同じ覚え方です。
鉄骨の完全溶込み溶接において、突合せ継手の余盛高さの最小値は0㎜
→完全溶け込みなので、0。
8とか10という数字に要注意!ひっかかるな!
裏当て金付きT継手の余盛高さの最小値、突き合わせる材厚さの1/4とし、材の厚さが40㎜を超える場合は10㎜
→あくまでも暗記方法として、裏金問題のTさん、証拠突き合わせる意思あつまる、しおどき。
裏金で、裏当て金付きを連想して、意思で、1/4、しお40、ど→十で10。
裏はつりT継手の余盛高さの最小値は、突き合わせる材の厚さの1/8とし、材の厚さが40㎜を超える場合は5㎜
→あくまでも暗記方法として、裏はつりから、裏口入学や裏口入社的な、方法で人生上手くいったTさんを想像。
事実を突き合わせるのは、イヤ、だから塩対応、ごめん。
イヤで1/8、しお→40、ごめん、5。

【平成28年の過去問を基にしています。】
1.ラフテレーンクレーンと油圧トラッククレーンを比較した場合、狭所進入、狭隘地作業性に優れるのは、【 ラフテレーンクレーン 】である。
クローラクレーンのタワー式と直ブーム式を比較した場合、ブーム下のふところが大きくより建物に接近して作業が可能なのは、【 タワー式 】である。また、定置式のタワークレーンの水平式と起伏式を比較した場合、つり上げ荷重が大きく揚程が高くとれるのは、【 起伏式 】である。
[覚えるポイントと覚え方]
問題文をよく読めば分かる問題です。
水平式と起伏式の違いは、ネットで画像検索するか参考書などを見れば分かります。
定置式のタワークレーンについて、日本の多くの建設現場では起伏式が多いと言えます。
過去門では正解はのタワー式が、✗直ブーム式という、ひっかけ単語になっての出題でしたから、要注意!
ラフテーについては、ラフな現場も得意だってー。ラフテー。みたいな感じいきましょう。
2.根切りにおいて、床付け面を乱さないため、機械式掘削では、通常床付け面上30~50cmの土を残して、残りを手掘りとするか、ショベルの刃を【 平 】状のものに替えて掲削する。
床付け面を乱してしまった場合は、粘性土であれば礫や砂質土などの良質士に【 置換 】するか、セメントや石灰などによる【 地盤改良 】を行う。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
令和4年と同じです。
これは文章そのままに読めばわかる問題でして、床付面を乱さないことが目標となります。
ひっかけキーワードに要注意で、爪状、水締め、鉛直。
砂質土には転圧。これは一次試験の復習ですから、過去ブログで説明で暗記方法を済みです。
杭の間を掘りすぎれば、そりゃ水平抵抗力に悪影響でしょっていうことで、鉛直は無視しましょう。
3.アースドリル工法は、アースドリル機の【 ケリーバ 】の中心を杭心に正確に合わせ、機体を水平に据え付け、掘削孔が鉛直になるまでは慎重に掘削を行い、表層ケーシングを鉛直に立て込む。
一般に掘削孔壁の保護は、地盤表層部はケーシングにより、ケーシング下端以深は、【 ベントナイト 】やCMCを主体とする安定液によりできるマッドケーキ(不透水膜)と【 水頭圧 】より保護する。
[覚えるポイントと覚え方]
過去問では、正解のケリーバが、ひっかけのクラウンという選択肢になっていました。
ベントナイトや、水頭圧については現場経験や、この試験勉強を通じて、なんとなく分かるはず。
ケリーバについては、バを、バーだと誤解して覚えれば、なんとなく分かるはず。
ドリル職人ケリーさんのバー、が由来の、ケリーバ※ウソです。
で覚えましょう!
4. 鉄筋のガス圧接を行う場合、圧接部の膨らみの直径は、主筋等の径の【 1.4 】倍以上とし、かつ、その長さを主筋等の径の【 1.1 】倍以上とする。
また、圧接部の膨らみにおける圧接面のずれは、主筋等の径の【 1/4 】以下とし、かつ、鉄筋中心軸の偏心量は、主筋等の【 1/5 】以下とする。
[覚えるポイントと覚え方]
一次試験用の過去ブログで紹介済みの、例の覚え方です。
今回の問題文用に、暗記フレーズを少しアレンジすると
→圧接部分は石(1.4倍)のように硬く、長さはイイ(1.1倍)感じで、ゴボーのように、1本まっすぐ(1/5)で、ずれは、ないし(1/4)。
5. 型枠に作用するコンクリートの側圧に影響する要因として、コンクリートの打込み速さ、比重、打込み高さ、柱や壁などの部位等があり、打込み速さが速ければコンクリートヘッドが【 大きく 】なって、最大側圧が大となる。
また、せき板材質の透水性または漏水性が【 大きい 】と最大側圧は小となり、打ち込んだコンクリートと型枠表面との摩擦係数が【 小さい 】ほど、液体圧に近くなり最大側圧は大となる。
[覚えるポイントと覚え方]
令和4年と同じです。
この問題は、文章通りですから、ひっかからないように言葉の意味を理解しておきましょう。
一般的に、型枠側圧とは型枠内に流し込まれた硬化前のコンクリートが型枠の側面に加える圧力だと言えます。
・コンクリートヘッドが大きくなると最大側圧が大となる。
→イメージとしては、夏の水遊びで、ホースの直径が大きくなれば、水量が増えて、ビニールプールの側面に高い圧力が掛かる。
・せき板材質の透水性文は漏水性が大きいと最大側圧は小
→水が漏れているなら、抵抗力というか、圧力は少ない。
・打ち込んだコンクリートと型枠表面との摩擦係数が小さいほど、液体圧に近くなり最大側圧は大となる
→例えば、固形物よりも半固形物の方が側圧大で、半固形物よりも液体の方が、側圧が大となる。
摩擦係数が大きいと、それが抵抗となり、側圧が減少するというイメージ。
※とにかくなにがなんでも、型枠表面との摩擦係数が小さいほど、液体圧に近くなり最大側圧は大と覚える。
6. 型枠の高さが【 4.5 】m以上の柱にコンクリートを打ち込む場合、たて形シュートや打込み用ホースを接続してコンクリートの分離を防止する。
たて形シュートを用いる場合、その投入口と排出口との水平方向の距離は、垂直方向の高さの約【 1/4 】以下とする。
やむを得ず斜めシュートを使用する場合、その傾斜角度は水平に対して【 30 】度以上とする。
[覚えるポイントと覚え方]
令和2年と同じです。
・コンクリートの分離防止、型枠高さ4.5m以上、たて形シュート投入口と排出口との水平方向の距離は垂直方向の高さの約1/2以下。
→あくまでも暗記術です。コンクリートの分離防止っていうのは、いい仕事っていうものを教えてくれる。
コンクリートと同じで、仕事とプライベートも、いい意味で分離しちゃいけないんだぜ。
高い場所でも、いい仕事をするためには、仕事は約1/2以下で、あとはプライベートも充実させなきゃって感じで。
しごと、し4、ご5、型枠高さ4.5m以上。あと約1/2以下も、この組み合わせで覚えます。
・やむを得ず斜めシュートを使用する場合で、シュートの排出口に漏斗管を設けない場合は、その傾斜角度を水平に対して30 度以上。
→とにかく30度を覚えればいいので。暗記術として。
シュートの排出口に漏斗管を設けないで、その傾斜角度を水平に対して30 度以上。に、できないヤツはサレ!
プライベートがなんだとか、ゴチャゴチャ言っているヤツはサレ!
シュートで流してやる!サレ!で、サ3レ0で、30度を覚えます。
7. 鉄骨工事におけるスタッド溶接部の15°打撃曲げ検査は、【 100 】本又は主要部材1個に溶接した本数のいずれか【 少ない 】方を1ロットとし、1ロットにつき【 1 】本行う。
検査の結果、不合格になった場合は同ーロットからさらに2本のスタッドを検査し、2本とも合格の場合はそのロットを合格とする。
これは、令和4年と、ほぼ同じです。
・スタッド溶接後の仕上がり高さ及び傾きの検査は100本又は、主要部材1本若しくは、1台に溶接した本数のいずれか少ないほうを1ロットとし、1ロットにつき1本行う
→あくまでも覚え方ですが、スタッドは、数字の1っぽいので、関連する数字は1が多いと覚える。
ポイントは100本ですが、検査なので100点を目指す、1番いい品質を目指す。という感じで100と1を覚えます。
補足ですが、スタッドの傾きなどは1次試験のおさらいですので、過去ブログの確認がオススメです。
8. トルシア形高カボルトの締め付け完了後の検査は、すべてのボルトについてピンテールが【 破断 】されていることを確認し、1次締め付け後に付したマークのずれを調べる。
ナット回転量に著しいばらつきが認められる群については、そのポルト一群の【 すべて 】のボルトのナット回転量を測定し、平均回転角度を算出し、ナット回転量が平均回転角度±【 30 】度の範囲のものを合格とする。
[覚えるポイントと覚え方]
これは完全に一次試験の復習問題です。
過去ブログで紹介して暗記方法で、いきましょう。
気をつける補足ポイントとしては、平均角度±30度を確実覚えて、全ての測定はイメージ通りで疑わないように。
もしもピンテールの破断がイメージできない場合には、ネットの資料や、参考書でよく確認しておきましょう。
一度でも見ていれば、納得できる内容です。

【平成22年の過去問を基にしています。】
1. 地盤の平盤載荷試験は、地盤の変形および支持力特性を調べるための試験である。試験は直径【 30 】㎝以上の円形の銅板に【 ジャッキ 】により垂直荷重を与え、載荷圧力、載荷時間、沈下量を測定する。また、試験結果より求められる支持力特性は、載荷板直径の1.5~【 2.0 】倍程度の深さの地盤が対象となる。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
令和4年と同じ問題。
数字と単語をしっかりと覚えましょう。
特に載荷係数という、ひっかけキーワードには要注意です。
※載荷係数:地盤に載荷試験を行い、圧力Pに対する沈下量Sによる計算式でK値(載荷係数)を求めます。
一般に、このK値が大きいほど、地盤は固く、変形しにくいと言えます。
直径30cm以上の円形の板にジャッキにより垂直荷重を与え、載荷圧力、載荷時間、沈下量を測定
→試験中だから、さわるんじゃねえ。で、さ3わ0、から30センチ以上だと連想して覚えます。
ジャッキにより垂直荷重を与え、載荷圧力、載荷時間、沈下量を測定
→荷重、圧力、時間、そして沈下量を測定。言葉通りの順番だと覚えておきましょう。
支持力特性は、載荷板直径の1.5〜2.0倍程度の深さの地盤が対象
→1.5〜2.0だと、そこまで深くはないと覚えておきましょう。
ただし、この範囲は確実に覚えておきたいので、暗記方法として。
イチゴ煮る。いちご(1.5)、にる(2.0)と覚えてください。
載荷試験、つまり圧力で潰します。
潰すものが、イチゴで、煮たイチゴなら、もうジャム。
載荷、圧力、いちごジャム、イチゴ煮る、1.5〜2.0倍。
これです。
2.根切りにおいて、床付け面を乱さないため、機械式掘削では、通常床付け面上30〜50cm
の土を残して、残りを手掘りとするか、ショベルの刃を【 平 】状のものに替えて掘削する。床付け面を乱してしまった場合は、礫や砂質土であれば【 転圧 】で締め固め、粘性士の場合は、良質土に置換するか、セメントや石灰などによる地盤改良を行う。また、抗間地盤の掘り過ぎや掻き乱しは、抗の【 水平 】抵抗力に悪影響を与えるので行ってはならない。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
令和4年と同じ内容です。
これは文章そのままに読めばわかる問題でして、床付面を乱さないことが目標となります。
ひっかけキーワードに要注意で、爪状、水締め、鉛直。
砂質土には転圧。これは一次試験の復習ですから、過去ブログで説明で暗記方法を済みです。
杭の間を掘りすぎれば、そりゃ水平抵抗力に悪影響でしょっていうことで、鉛直は無視しましょう。
3.場所打ちコンクリート地業のオールケーシング工法において、掘削は【 ハンマーグラブ 】を用いて行い、1次スライム処理は、孔内水が【 多い 】場合には、【 沈殿パケット 】を用いて処理し、コンクリート打込み直前までに沈殿物が多い場合は、2次スライム処理を行う。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
オールケーシング工法、地表面下10m程度までのケーシングチューブの初期の圧入精度によって以後の掘削の鉛直精度が決定
→10mまでが重要、10、10カウント、ボクシング的なスポーツを連想して覚えましょう。
ハンマーグラブを用いて行い、一次スライム処理は、孔内水が多い場合には、沈殿バケットを用いて処理
→ハンマーグラブと沈殿バケットのセットを覚えます。
ハンマーグラブ、ハンマーグローブ、なんだかボクシング的なスポーツが連想できますよね。
ハンマーグラブで、一撃KO、相手は沈殿していくーみたいな連想です。
この2つの連想フレーズを合わせて覚えれば、キーワードと数字が、さくっと丸暗記できますね。
✗ドリリングバケット✗などの、不正解のひっかけキーワードには要注意です。

4.隣接する鉄筋の継手のずらし方において、ガス圧接継手とする場合は、隣り合う鉄筋のガス圧接の位置を【 400 】㎜以上となるようにずらす。
また、重ね継手とする場合は、隣り合う重ね継手の中心位置を、重ね継手長さの約【 0.5 】倍ずらすか、【 1.5 】倍以上ずらす。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
過去問では正解の400が、300という、ひっかけ数値になっていたので、気をつけましょう。
・圧接継手及び、機被式継手の隣り合う位置は、400ミリ以上ずらす。
・重ね継手の位置は、0.5倍または、1.5倍以上ずらす。
さあ、しっかりと数値を覚えましょう。あくまでも暗記方法として、説明してきます。
まず、すぐに鉄筋で、エイって愛のムチならぬ、愛の鉄筋をふりまわす人を想像しましょう。
男でも女でも女王様でも構いません。
しっかりとイメージできたら、次の暗記フレーズで丸暗記です。
やばい。
あのお方が大切にしていた花が、しおれてしまった。(村人AとB)
知られたら、怒られてしまう、鉄筋で。(村人A)
行こ、逃げよう!絶対に言うなよ、鉄筋で、やられてしまうから。(村人B)
というストーリーで覚えます。
ストーリーの流れは↓
しおれた、知られたら、怒られる、行こ、言っちゃダメだ!
となり、つまりは、
し(4)お(0)れ(0)た、知(4)ら(0)れ(0)たら、怒(05)られる、行こ(15)、言っちゃダメ(1.0じゃダメ)だ!
これでとにかく、400と、0.5と1.5を覚えます。
はい、丸暗記!できたはずです。

5.ガス圧接の技量資格種別において、手動ガス圧接については、1種から【 4種 】まであり、2種、3種、4種となるに従って、圧接作業可能な鉄筋径の範囲が【 大きく 】なる。技量資格種別が1種の圧接作業可能範囲は、異型鉄筋の場合は呼び名D【 25 】以下である。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
令和2年と同じです。
一次試験の過去ブログで、暗記方法は説明済みの内容です。
あとは、言葉の組み合わせですが、手動、なので、人の手、人、有資格者、有資格という連想で手動=有資格。
あとの資格種類ごとの作業可能範囲は過去ブログを御覧ください。
6.型枠に作用するコンクリートの側圧において、比較的軟らかいコンクリートをコンクリートポンプで急速に打ち上げる場合、打込み速さが速ければ、コンクリートヘッドが【 大きく 】なって、最大側圧が大となる。また、コンクリートが軟らかければ、コンクリートの内部摩擦角が小さくなり、液体圧に近くなり側圧は【 大 】となる。同じ軟らかさの普通コンクリートと軽量コンクリートを同じ打込み速度で打設した場合の側圧は、軽量コンクリートの方が【 小さい 】。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
令和4年と同じです。
この問題は、文章通りですから、ひっかからないように言葉の意味を理解しておきましょう。
一般的に、型枠側圧とは型枠内に流し込まれた硬化前のコンクリートが型枠の側面に加える圧力だと言えます。
・コンクリートヘッドが大きくなると最大側圧が大となる。
→イメージとしては、夏の水遊びで、ホースの直径が大きくなれば、水量が増えて、ビニールプールの側面に高い圧力が掛かる。
・せき板材質の透水性文は漏水性が大きいと最大側圧は小
→水が漏れているなら、抵抗力というか、圧力は少ない。
・打ち込んだコンクリートと型枠表面との摩擦係数が小さいほど、液体圧に近くなり最大側圧は大となる
→例えば、固形物よりも半固形物の方が側圧大で、半固形物よりも液体の方が、側圧が大となる。
摩擦係数が大きいと、それが抵抗となり、側圧が減少するというイメージ。
※とにかく、なにがなんでも、
型枠表面との摩擦係数が小さいほど、液体圧に近くなり最大側圧は大と覚える。
7.日本産業規格(JIS※出題時は旧名称の日本工業規格)のレディーミクストコンクリートの規格では、指定がない場合のレディーミクストコンクリートの塩化物含有量は、荷卸し地点で【 塩化物イオン 】量として0.30kg/㎥以下とされている。また、レディーミクストコンクリートに使用する【 砂 】の塩化物量については、プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材に用いる場合を除き、【 NaCI 】換算で0.04%以下と規定されている。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
これは、やや難しい問題ではあるが、文章と単語の組み合わせを覚えておけば何とかなるはず。
過去問では、正解の砂。が、なななんと砂利に変更されていました。完全にひっかけの選択肢です。
・レディーミクストコンクリートの塩化物量はJIS規定がある。
・レディーミクストコンクリート用骨材、砂は塩化物量の規定あるが、砂利は塩化物量の規定がない。
・荷卸し地点で塩化物イオン量として0.30kg/㎥以下
→あくまでも暗記術として、荷卸し地点で見れないくらい少なければOK。見れない(見えない)、み3、れ0。
少ないという前提なので、3と0が分かれば、0.30まで連想できるように暗記。
・レディーミクストコンクリートに使用する砂の塩化物量については、プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材に用いる場合を除き、NaCI換算で0.04%以下と規定されている。
→塩化物、塩、塩って砂みたい、砂って塩みたい、で、砂だと覚えておきます。
NaCI換算で0.04%以下は、 NaCIを、ナチュラルなシオの略だとムリヤリ誤解して覚えてみます。
Naナチュラルなciシオ、おしお、お0し4お0で、0.040%みたいな理解で覚えます。
8.鉄骨工事現場で用いられる主な溶接法には、被覆アーク溶接、ガスシールドアーク溶接、セルフシールドアーク溶接がある。それらを比較した場合、【 被覆アーク溶接 】は全姿勢溶接が可能であり、【 ガスシールドアーク 】溶接は作業能率が最もよい。また、ガスシールドアーク溶接は、セルフシールドアーク溶接と比較して風に対して【 弱い 】。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・ガスシールドアーク溶接は、セルフシールドアーク溶接と比較して風に対して弱い。
→これは知っていれば当たり前だが、知らないと分からないので、イメージで覚えよう。
ガスシールドアーク、ガスのシールド、そりゃ風に弱いよね。
セルフシールドアーク、セルフをオートシールドガードシステム的な理解をしてみる。
自動でシールドでガードするロボットの機能みたいだと覚えてみる。という方法があります。

※あくまでも本ブログは試験対策の暗記用の解説です。正確な情報は各公式HP等をご確認ください。
↑無料NOTEを書きました。読むと、やる気が出て暗記効率が上がりますから、試験勉強の合間に読むことをオススメします。
2次試験の効率的な勉強法も、過去問を解き続けること。
過去問の重要性
とにかく出題範囲が広いため、本、アプリ、他のサイトでも、なんでもよいので過去問を解くことが最重要。
なぜなら、例年、過去問から選択肢が出題されていますから、正解の選択肢を多く覚える事が、合格の近道です。
そして、記述問題対策としては、とにかく書くことが重要。より丁寧に、単語は正確に、漢字も覚えましょう。
テーマごとの回答例を、しっかりと準備しておきましょう。
語呂合わせの活用
試験対策としては、正確な数字の丸暗記が必須です。
実は、一次試験のために学んだ知識が活かせる問題が多いです。
ただし、文章の中の穴あきを埋める穴埋め問題形式が多い為、今まで以上に長く全体を覚える必要があります。
法規法令の確認も大事。
労働安全衛生法や建築基準法などは、改正される事があります。
このブログは2024年の法律を基にしていますから、最新の法規法令を常に確認し、正確な情報を得ることが重要。
各公式HPを定期的にチェックし、アップデートされた情報に注意を払うことが大切で、これは現場で活きる知識です。
本日も、お読みいただき、ありがとうございます。


コメントをお書きください