↑無料NOTEを書きました。読むと、やる気が出て暗記効率が上がりますから、試験勉強の合間に読むことをオススメします。
1級建築施工管理技術検定試験【二次検定問題】の覚え方と勉強法
このブログは2024年基準の情報をもとに、一級建築施工管理技術検定に出題される可能性がある問題の覚え方や、
法規法令や過去問の重要性を強調し、独自の見解を提供しますが、正確な情報は各公式HP等でご確認ください。
※あくまでも暗記方法は試験対策用の説明として御理解ください。
※二次試験向けの内容です。一次試験の勉強や、復習は↑にあるリンクの、一次試験まとめ一覧がオススメです。
今回のテーマ
【 一次試験復習系の対策[法文] 】
今回のテーマは、一次試験の延長線上にある問題と言える[法文]です。
一次検定50点超えの高得点であれば覚えているかもですが、一次試験まとめ一覧を全て復習しておくことがオススメです。
ここでは、過去に出題された穴埋め問題を基に覚えるポイントを紹介していきます。
【 】内の単語と、赤文字は穴抜きされる可能性がある重要キーワードです。
攻略方法は、ひとつしかありません。
法文なので、正確にキーワードを丸暗記。
それしかありません。では、いきましょう。
※あくまでも暗記用ブログですので、正確な情報は各公式ホームページをご確認ください。
【令和6年の過去問を基にしています。】
次の各法文において、【 】に当てはまる正しい語句を、下の該当する枠内から1つ選びなさい。
■1. 建設業法(施工体制帳及び施工体系図の作成等)
第24条の8 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び【 工期 】その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2
3.
4
(略)
(略)
第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、
当該建設工事における各下請負人の施工の【 分担 】関係を表示した施工体系図を作成し、
これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
政令で定める金額以上になるときは建設工事の内容と工期、の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置く。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・施工体制台帳は、内容と工期が重要。
暗記方法として、ここでの施工体制台帳は厚めの週刊マンガ雑誌サイズで、叩きやすい物をイメージします。
内容が無いよう、だと好機になってしまうから、施工体制台帳が必要だと覚えましょう。
好機とは、チャンスのことです。
内容がない、とサボる好機(こうき)になるので、サボったら、施工体制台帳で、おしおきです。
または、内容がないよう、かつ工期がないと、それは、下請けを不法に無限に働かせるチャンスです。
施工体制台帳を武器に、言うことを聞かせるかもしれません。
無論、それらはダメなので、施工体制台帳は内容と工期(こうき)が重要だと覚えます。
・各下請負人の施工の【 分担 】関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
ここの覚え方は教室をイメージします。
掃除の分担表みたいな感じです。
だれが当番か、責任を明確にするために有効です。
小学校とか、職場にもあるかもしれません。
施工体系図については、掃除をする姿勢などイラスト化した
施工体型図みたいなものを想像して覚えましょう。

【ついでに絶対に覚えておくポイント!】
・特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合〜
→この文章の発注者とは、施主です。
施主、レストランで言えば客、オーダーする人、発注をする人、発注者だと覚えておきましょう。
注文を発する人で、発注者です。
※発注者以外の単語は要注意!ひっかけの選択肢には気をつけましょう。
・下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び〜
→施主は元請負人のことは分かりますし、打ち合わせや書類手続きをすることも多いでしょう。
しかし、下請負人ことは分かりませんので、施主の為に、重要項目には、施工体制台帳に記載。
とにかく、特に下請人のことは、施主のためにも、施工体制台帳に残すと覚えましょう。
もちろん、下請け会社の企業名等が変更となった場合にも同様です。

【超要注意ポイント】
第24条の6 特定建設業が【 】となって下請け契約〜
この法文のケースでは、【 注文者 】が正解です。
ひっかけの選択肢として予想される、施主や発注者というキーワードに要注意!
施主=発注者という表現のルールを覚えておきましょう。
[ 第24条の6 特定建設業が注文者となって下請け契約〜 ]

■2.建築基準法施行令(建て方)
第136条の6 建築物の建て方を行なうに当たっては、【 仮筋交い 】を取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
2. 鉄骨造の建築物の建て方の【 仮締め 】は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。
覚え方:建て方のときに、取り付けるとなれば、仮筋交いしかない。
そして、鉄骨造の建て方のときに行うのは、仮締め。
※仮筋交いと仮締めが入るポイントが重要、単語を入れ替えた文章に注意!
覚えるイメージとしては、ヤンキー漫画などでは、しめる、と言えばボコボコにするというイメージですよね。
これを利用して、鉄骨造のときは、倒壊防止のために、仮締めをするわけなので。
仮締めなので、倒壊しない。
つまり、仮でしめているので、倒れない。という覚え方か、
権力構造が倒壊しないように、仮でしめておくか、というイメージ。
※仮筋交いと仮締めが入るポイントが重要、単語を入れ替えた文章に注意!
・建て方で、取り付けるのは、仮筋交い。
・鉄骨造の建て方のときに倒壊防止で行うのは、仮締め。

■3.労働安全衛生法(事業者の講ずる措置)
第71条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な【 職場 】環境を形成するように努めなければならない。
一 作業環境を快適な状態に【 維持管理 】するための措置
二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四 前三号に掲げるもののほか、快適な【 職場 】環境を形成するため必要な措置
・維持管理と言えば、職場環境しかない。
労働者の疲労を回復と言えば、休憩所。
労働環境とか保守などのキーワードに惑わされるな!
意地(いじ)でも維持(いじ)管理するのは、職場環境!
職場(しょくば)は、食場(しょくば※お菓子を食べるところ)とか色場(職場※色恋、恋、社内恋愛、不倫や浮気をするところ)とか、なんかそういう連想で覚えましょう。
だからこそ、意地でも職場環境を維持するんじゃいって感じで覚えます。

【令和5年の過去問を基にしています。】
■1.建設業法(下請代金の支払)
第24条の3 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から【 1月 】以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2.前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち【 労務費 】に相当する部分については、
現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3(略)
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
請負契約の下請けでも、労務費は給料みたいなもんだから1月以内で払え、やった後は速攻で払え。
労務費は人件費みたいなものだから、すぐ払え、現金で払え。
キーワードとしては、出来高という言葉で、仕事の成果や実績とか結果だと思えば理解しやすいはず。
一般に下請け業者は、社員とは違い、きびしい条件で仕事をするケースがあります。
やればやっただけ稼げる人もいれば、請負契約なので、社員とは違い結果がすべての厳しいときもあるはず。
そして、どうしても力関係としては、元請け様には逆らえないこともあるかも。
下請け会社と言っても、一人親方、一人社長、個人事業主もいて、下請けイジメから守る必要があるということで。
この法律です。とイメージしましょう。
1人の職人が仕事をした成果、それはつまり出来高です。
家賃、光熱費、携帯代、あらゆる支払いは毎月発生しますから、やっぱり月一で金が欲しいのよ。
下請けの見積もり上、労務費は、手伝いで呼んだ仲間への支払いや、雇っている従業員の給料なのよ。
だから、それを倒産しかけている会社とかが手形とか不安定な支払い方法で払うと、最悪共倒れしちゃいますよ。
ただし、経営が厳しい元請けのことも守ることも法律の役目なので、元請負人は支払いを受けたときでいいよ。
現金で支払うことは、配慮でいいよ。
と、言うことで。
元請負人は支払いと受けたとき、下請人へ出来高分は、1月以内に支払わなければならない。
あと、労務費は、いつもニコニコ現金払いでよろしくね。と覚えておきましょう。
労務費→給料→月1回→1月以内というイメージでいきましょう。

■2. 建築基準法施行令(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
第136条の3 建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
2(略)
3(略)
4
建築工事等において深さ【 1.5 】メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。
5(略)
6 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なうこれを安全な状態に雑持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の【 沈下 】による危害を防止するための措置を講じなければならない。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
この法文は覚えておきたいポイントが多いので、しっかり確実に暗記しておきましょう。
まずは、言葉の組み合わせで丸暗記をトライしていきましょう。
根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合とは、地面を掘ります。
だから、ガス管、電線、水道管などの埋設物には要注意!!!
※一般にケーソン工事とは、橋梁の基礎や防波堤・岸壁などの港湾構造物の土台として、コンクリートや鋼鉄製の巨大な箱とも呼べるケーソンを地盤に沈めて設置する工法です。
根切りで1.5mがポイントです。
これは一次試験で学んだことを思い出しましょう。
※過去ブログを要チェック!
根切りときたら、山留めが必須で、山留めとなると点検と排水がセットです。
山留めと点検と排水がセットだから、矢板等を抜取るときは、周囲の地盤沈下による危害を防止する処置が必要。
根切り→山留め→点検&排水→矢板を抜くリスク→周囲の地盤沈下という言葉の組み合わせを丸暗記です。
■3. 労働安全衛生法(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を総括管理させなければならない。
一 労働者の【 危険 】又は健康障害を防止するための措置に関する
こと。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び【 再発 】防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
技術により危険を取り除き、再発を防止する。というイメージで覚えます。
これも言葉の組み合わせが重要です。
事業者が事業所ごとに、安全衛生教育を行い、労働災害の調査ときたら再発防止。
労働災害の調査をするのは、再発防止のため。という連想で暗記です!
※※危険と労働災害等が混同しないように要注意です。
ひっかけの選択肢として出題の可能性大!

【ついでに確実に覚えておく暗記ポイント】
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を総括管理させなければならない。
一 労働者の【 危険 】又は健康障害を防止するための措置に関する
こと。
→あくまでも、暗記術として。
事業者は、事業場ごとに、安全衛生を厳守するために、最強の管理者として、全てにおいて勝つ最強の管理者、
総勝安全衛生管理者を選任して、その部下に、安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者がいるというイメージ。
あくまでも暗記術で、その最強の管理者の目的は、労働者による反乱を防ぐという意味で、気・剣(きけん)を防止。
そして、未来永劫働かせるために、棄権(きけん)の防止。
という、おそろしいイメージで丸暗記です!

【令和3年の過去問を基にしています。】
■1.建設業法(請負契約とみなす場合)
第24条 委託その他いかなる【 名義 】をもってするかを問わず、【 報酬 】を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
委託、名義、報酬、完成、締結というキーワードが重要です。
まず、請負契約と聞けば、契約締結が連想でき、注文者が契約をする目的は、工事の完成です。
そして、請負者の目的は報酬となります。
最後に、仕事を委託するためには、契約書が必要なので、契約書と聞けば名義人で名義。
という連想でいくか、委託でも契約書でも口約束でも、どんな名称でも義理を果たすことこそが請負契約。
みたいな、とにかく、名義というキーワードを覚えておきましょう。

■2.建築基準法施行令(建て方)
第136条の6 建築物の建て方を行なうに当たっては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による【 倒壊 】を防止するための措置を講じなければならない。
2 鉄骨造の建築物の建て方の【 仮締め 】は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
仮にしめるから、倒壊はしない。
ヤンキー漫画風の言葉では、しめるとは、痛めつけて言うこと聞かせることみたいなイメージだとして。
またボコボコにしてはいない、仮でしめているから、相手は立っている、つまり倒壊はしていない。
そんなイメージで丸暗記です。
建て方のとき、取り付けるというキーワードがあれば、それは仮筋交い(かりすじかい)しかありません。
と、覚えていきましょう。
3, 労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)
第29条 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な【 指導 】を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれ基づく命令の規定に違反していると認めるときは、【 是正 】のため必要な指示を行なわなければならない。
3(略)
指導しないと、死動につながる。是正とは、是すなわち正義なり。みたいな武士道精神、日本男児的な感じで覚える。

【令和2年の過去問を基にしています。】
■1.建設業法に基づく建設工事の完成を確認するための検査および引渡しに関する次の文章において、【 】に当てはまる語句または数値を記入しなさい。
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、
当該通知を受けた日から【 20 】日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
元請負人は、前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。
ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から【 20 】日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の【 特約 】がされている場合には、この限りでない。
■2,「建築基準法施行令」に基づく山留め工事等を行う場合の危害の防止に関するの文章において、【 】に当てはまる語句を記入しなさい。
建築工事等における根切りおよび山留めについては、その工事の施工中必要に応じて【 点検 】を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の【 沈下 】による危害を防止するための措置を講じなければならない。
■3.「労働安全衛生法」に基づく総括安全衛生管理者に関する次の文章において、【 】に当てはまる語句を記入しなさい。
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者または第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の【 危険 】または健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全または衛生のための【 教育 】の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるもの。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・下請けを守る法律であるから、20日以内かつできる限り短い期間に点検と理解する。
そして、点検で◎二重丸、よくできました!となってから支払い→点検は二重丸で20と覚える。
下請けを守る法律であるから、例外的に特別な約束を交わした場合、つまり特約として、
20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
だと覚えます。
・山留め関連は連想で暗記します。山留め、危険、点検、排水が重要、矢板抜取りする、地盤沈下リスクに注意。
・安衛法関連でいくと、事業者は労働者を家族レベルで守りなさい。という法律だと拡大解釈をしてみます。
家族だから、危険からも健康障害からも守る。
しかし、労働者であるから、事業者は労働災害について防止をする。
事業者だからこそ、責任をもって労働災害の再発防止もする。
危険又は健康障害とは、労働者の安全と健康の障害となるもの、有害な環境や過酷な労働環境。
あと、安全衛生ときたら教育。
というイメージで、言葉の組み合わせを暗記していきます。
※※ここでも、とにかく絶対に、危険と労働災害等が混同しないように要注意です。
ひっかけの選択肢として出題の可能性大!

【令和元年の過去問を基にしています。】
問題6
次の1.から3.の問いに答えなさい。
■1.「建設業法」に基づく主任技術者および監理技術者の職務等に関する次の文章において、【 】に当てはまる語句を記入しなさい。
主任技術者および監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、
当該建設工事の【 施工計画 】の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理および当該建設工事の施工に従事する者の技術上の【 指導監督 】の職務を誠実に行わなければならない。
■2.「建築基準法施行令」に基づく落下物に対する防護に関する次の文章において、【 】に当てはまる語句または数値を記入しなさい。
建築工事等を行う場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が【 5 】m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を【 鉄網 】または帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
■3.「労働安全衛生法」に基づく特定元方事業者等の講ずべき措置に関する次の文章において、【 】に当てはまる語句を記入しなさい。
特定元方事業者は、その労働者および関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる【 労働災害 】を防止するため、【 協議組織 】の設置および運営を行うこと、作業間の連絡および調整を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に関する指導および援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・監理技術者の役割は、建設工事を適正に実施するため、施工計画作成、工程管理、品質管理、その他技術上管理及び施工従事者の指導監督をする。
適正に実施するために、その基準となる計画として施工計画を作成し、工程を管理しつつ、品質管理もする。
その他技術管理及び、施工従事者の指導監督をしないと、危険作業によるケガや事故、最悪の場合は死にいたる。
つまり、死への道、デスロードを施工従事者が進まないように、死道(しどう)に進むような死動(しどう)死の動きをしないように、指導監督をしないといけません。と覚えます。
・落下物に対する防護については、鉄網または帆布(はんぷ)だと覚えておきましょう。
※帆布の覚え方は、 帆船の帆として使われていたという語源から、落下物を受け止められそうというイメージで。
工事現場の境界線から水平距離が【 5 】m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上の覚え方は、
ごめんなさい。とならないように、対策をする。
ご(5)めんなさい。とな(7)らないで、5と7を覚えます。
ごめんなさいと頭を水平に下げるイメージで、5は水平だと理解しておきましょう。
7が高さという連想暗記術としては、ひらきなおるな!ひらきな(7)おるな(7)!
開き直って姿勢がよく立っているイメージで、7mが高さだと暗記します。
・特定元方事業者は、その労働者および関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置および運営〜の覚え方としては、
特定元方事業者の工事現場は、特に複数名での作業が予想される。
そして、労働災害を防止するためには、協議組織、お互いに協議して、各下請け業者のトップダウンで実現をする。
安全のために、教育、指導、援助を行う。
現場で、言うだけでは、効果的ではない。
というイメージで各キーワードを覚えましょう。
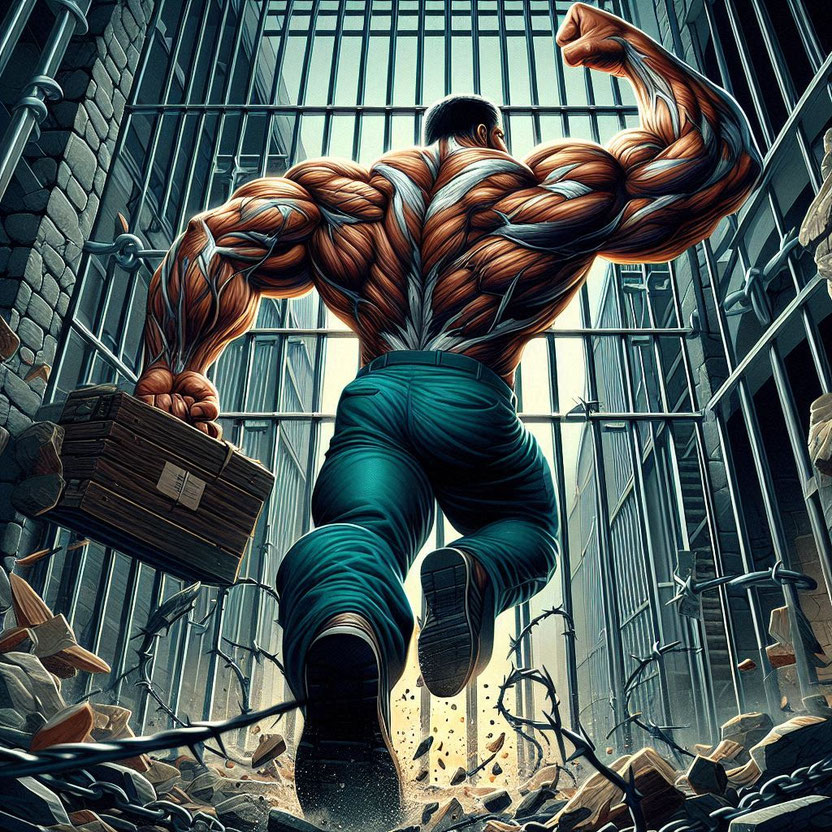
【重要暗記ポイントを補足】
あくまでも暗記術として、危害というキーワードと文章の組み立てを覚えましょう。
工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれ〜
危害を生ずるおそれが、あるから、
工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上、
鉄網または帆布で危害を防止する。
危害について、あくまでも暗記術として、危険なガイ、危険なGUYというイメージで、
きがい、危GUY、で、危害を連想してみます。
ヤツを止めるには、鉄網または帆布しかない!って感じで覚えるといいでしょう。
ヤツが野に放たれたら、ごめんなさいじゃすまないぞーって感じで、5と7も覚えられます。

【平成30年①の過去問を基にしています。】
問題6
次の1.から3.の問いに答えなさい。
■1.「建設業法」に基づく建設工事の見積り等に関する次の文章において、【 】に当てはまる語句を記入しなさい。
建設業者は、建設工事の【 請負契約 】を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の【 経費 】の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
■2.「建築基準法施行令」に基づく仮囲いに関する次の文章において、【 】に当てはまる語句または数値を記入しなさい。
木造の建築物で高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるものまたは木造以外の建築物で【 2 】以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替または除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より【 低い 】場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。
ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合または工事現場の周辺もしくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
3.「労働安全衛生法」に基づく事業者等の責務に関する次の文章において、【 】に当てはまる語句を記入しなさい。
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、【 工期 】等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある【 条件 】を附さないように配慮しなければならない。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
つまり、ざっくりとドンブリ勘定は駄目、材料費と労務費その他経費がわかるように見積もりをして。
ということだとイメージして覚えましょう。
工事を進めるために経費は重要かつ必要、経費を全て細かく正確に見積もりをするのは無理なこともあるから、務めるという感じの法文で努力義務になっているという風に覚える。
・仮囲いの基準について
あくまで覚え方として、13mでは意味(い1、み3)がない、9mは苦しい(く9るしい)と覚える。
仮囲いを設置したくない言い訳としてのイメージをして暗記をしてみる。
13mまでは意味が無いと断れて、軒高9mくらいの木造ではコスト的に苦しいと、でもそれらの数字を超えたら、
言い訳は通用せず、仮囲いが必要となる。
つまり、木造の建築物で高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるものまたは木造以外の建築物で2以上の階数を有するものは、仮囲いが必要。
※周辺環境及び工事状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
そして木造以外は、危険が多いし規模も大きいから、2階以上は原則として仮囲いが必要。
1.8は、仮囲いがないとイヤ(い1や8)で、1.8mの基準は、あくまでも仮囲いなので、低い地盤であれば、周囲の地盤の高さに合わせる。
他の暗記方法としては、ズバッと言い切るフレーズで、
『意味(13)がある高さ、苦(9=く、る)しみをなくす。』
とにかく、13と9を覚えましょう!
・労働安全衛生法関連、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
つまり、他人に請け負わさせるなら、重要なことは施工方法と工期等である、だからこそ、それらについて現場行ってみたら最悪で地獄みたいでした。
でも請け負っちゃったから断れない。。。
みたいな、悪質な条件を附さないように配慮が必要というイメージで覚える。

【平成30年②の過去問を基にしています。】
次の1.から3.の問いに答えなさい。
■1.「建設業法」に基づく特定建設業者の下請代金の支払期日等に関するあの文章において、【 】に当てはまる語句または数値を記入しなさい。
特定建設業者が【 注文者 】となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者または資本金額が4,000万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金の支払期日は、下請負人からその請け負った建設工事の完成した旨の通知を受け、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が当該建設工事の引渡しを申し出た日(下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合にあっては、その一定の日。)から起算して【 50 】日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
■2.「建築基準法施行令」に基づく落下物に対する防護に関する次の文章において、【 】に当てはまる語句または数値を記入しなさい。
建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地面からの高さが【 3 】m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、【 ダストシュート 】を用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
■3.「労働安全衛生法」に基づく元方事業者の講ずべき措置等に関する次の文章において、【 】に当てはまる語句を記入しなさい。
元方事業者は、関係請負人または関係請負人の【 労働者 】が、当該仕事に関し、この法律またはこれに基づく【 命令 】の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・特定建設業者が注文者となった下請契約では、建設工事の完成した旨の通知を受け、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が当該建設工事の引渡しを申し出た日から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
覚え方としては、特定建設業者は50日以内に支払ってください。
そうしないと、、、この覚え方は過去ブログをチェック!
あとは注文者というキーワードは、オーダーをするというイメージで覚えます。
※発注者や元請などの、ひっかけキーワードにご注意ください!
・工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合〜の覚え方。
境界線近くではゴミを上から投げるな!というイメージで覚える。
境線近く(水平距離)ではゴ(5)ミ(3)を上(地面からの高さ)から投げるな!
ダストシュートについては、言葉そのままか、ダスト(ゴミ)シュート!って感じで、ゴミを蹴るイメージか、ゴミがダストシュートを勢いよく通るイメージで覚えましょう。
・元方事業者は、関係請負人または関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律またはこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
あくまでも覚え方として、現場にいる労働者の法令遵守とは、法律と、それと同等に尊い元方事業者様からのご命令のことである!
みたいな感じで、元方事業者、労働者、命令、是正指示、というキーワードを覚えましょう。
労働者は法律と命令に従え!是正指示とは、コレ正しいと、支持せよ!みたいな。感じで暗記です。

【平成29年の過去問を基にしています。】
問題6
次の1.から3.の問いに答えなさい。
「建設業法」に基づく元請負人の義務に関する次の文章において、【 】に当てはまる語句を記入しなさい。
■1.特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の【 分担 】関係を表示した【 施工体系図 】を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
■2.「建築基準法施行令」に基づく工事現場の危害の防止に関する次の文章において、【 】に当てはまる語句を記入しなさい。
建築工事等における根切りおよび山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、【 排水 】を適当に行う等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の【 沈下 】による危害を防止するための措置を講じなければならない。
■3.「労働安全衛生法」に基づく労働者の就業に当たっての措置に関するの文章において、【 】に当てはまる語句を記入しなさい。
事業者は、その事業場が建設業に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接【 指導 】または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全または衛生のための教育を行なわなければならない。
- 作業方法の決定および労働者の配置に関すること
二 労働者に対する【 指導 】または監督の方法に関すること
三 前二号に掲げるもののほか、【 労働災害 】を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
これは施工体系図により、各下請けの責任を明確化するため、施工の分担関係を明らかにすることが目的。
イメージとしては、学校や職場の掃除当番表という感じでしょうか。
施工体系図、分担というキーワードを覚えましょう。
・土留めといえば、点検と排水で、リスクは地盤の沈下です。
・労働安全衛生法、覚えておくキーワードは、指導と労働災害。
あくまでも暗記術として、職長は先生みたいな存在、ときには先輩かもしれないから指導、そして監督だと指導者だから、指導がイメージしやすい。
防ぐ災害としては、自然災害は防ぎきれないから、労働災害を防ぐというイメージで覚えます。

【平成28年の過去問を基にしています。】
問題6
1.建設業法に基づく主任技術者および監理技術者に関するの文章において、【 】にあてはまる語句を記述しなさい。
主任技術者および監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の【 施工計画 】の作成、【 工程管理 】、品質管理その他の技術上の管理および当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2.建築基準法施行令に基づく建て方に関する次の文章において、【 】にあてはまる語句を記述しなさい。
建築物の建て方を行うに当たっては、【 仮筋交い 】を取り付ける等荷重または外力による【 倒壊 】を防止するための措置を講じなければならない。
■3.労働安全衛生法に基づく健康診断に関する次の文章において、【 】にあてはまる語句を記述しなさい。
事業者は、【 有害 】な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、【 医師 】による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・施工計画という基準があるからこそ、工程管理があり、品質管理ができて、それが技術的指導とつながる。
・建て方のときに、取り付けるので、仮筋交いしかない。建て方なので、防ぐリスクは倒壊しかない。
・暗記方法として、有害な環境下の業務では、特別な項目の健康診断が必要ですが、それにはコストが掛かる、
法の抜け穴を防ぐため、医師という項目を追加して、誰かがテキトーに診断しちゃダメという話し。
有害仕事、ゆうがいしごと、ユーが医師ゴトー、YOUが医師ゴトウ、という感じで丸暗記。
有害と医師をセットで覚えておきましょう。

【ついでに覚える重要暗記ポイントを補足】
主任技術者および監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため〜
主任技術者の基本原則を覚えておきましょう。
主任技術者とは、元請・下請を問わず配置され、施工計画や工程・品質・安全を管理する現場責任者。
・原則「元請・下請を問わず配置義務あり
・例外もあり「軽微な工事」「特定の専門工事のみ請負」等
・原則「兼任不可※緩和条件あり」※※監理技術者との兼任不可、専任義務がある場合は他現場と兼任不可。
上記のような特徴を、しっかり覚えておきましょう。
あくまでも、覚え方としてですが、しゅにんぎじゅつしゃ、を、守忍技術者と誤解して覚えると、
なんとなくイメージ通り、なはずです。
常にいる、技術ある、兼任できないできない的な。

【平成27年の過去問を基にしています。】
問題6
■1.「建設業法」に基づく建設工事の請負契約に関するの文章において、【 】にあてはまる語句を記述しなさい。
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の【 経費 】の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
建設業者は、建設工事の【 注文者 】から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。
■2.「建築基準法施行令」に基づく工事現場の危害の防止に関するの文章において、国にあてはまる語句又は数値を記述しなさい。
木造の建築物で高さが13m若しくは【 軒の高さ 】が9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが【 1.8 】m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。
ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
■3.「労働安全衛生法」に基づく元方事業者の講ずべき措置等に関するの文章において、【 】にあてはまる語句を記述しなさい。
建設薬に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において【 関係請負人 】の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該【 関係請負人 】が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の【 指導 】その他の必要な措置を講じなければならない。
[ 覚えるポイントと覚え方 ]
・建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
つまり、ざっくりとドンブリ勘定は駄目、材料費と労務費その他経費がわかるように見積もりをして。
ということだとイメージして覚えましょう。
工事を進めるために経費は重要かつ必要、経費を全て細かく正確に見積もりをするのは無理なこともあるから、務めるという感じの法文で努力義務になっているという風に覚える。
・仮囲いの基準について
あくまで覚え方として、13mでは意味(い1、み3)がない、9mは苦しい(く9るしい)と覚える。
仮囲いを設置したくない言い訳としてイメージして暗記をしてみる。
13mまでは意味が無いと断れて、軒高9mくらいの木造ではコスト的に苦しいと、でもそれらの数字を超えたら、
言い訳は通用せず、仮囲いが必要となる。
つまり、木造の建築物で高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるものまたは木造以外の建築物で2以上の階数を有するものは、仮囲いが必要。
※周辺環境及び工事状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
そして木造以外は、危険が多いし規模も大きいから、2階以上は原則として仮囲いが必要。
1.8は、仮囲いがないとイヤ(い1や8)で、1.8mの基準は、あくまでも仮囲いなので、低い地盤であれば、周囲の地盤の高さに合わせる。
・元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
覚えるキーワードは関係請負人と指導です。
危険を防止するのは技術である。
それを元方事業者は、関係請負人へ指導しなければならないと理解すれば、絶対に完璧に覚えられます。

※あくまでも本ブログは試験対策の暗記用の解説です。正確な情報は各公式HP等をご確認ください。
↑無料NOTEを書きました。読むと、やる気が出て暗記効率が上がりますから、試験勉強の合間に読むことをオススメします。
2次試験の効率的な勉強法も、過去問を解き続けること。
過去問の重要性
とにかく出題範囲が広いため、本、アプリ、他のサイトでも、なんでもよいので過去問を解くことが最重要。
なぜなら、例年、過去問から選択肢が出題されていますから、正解の選択肢を多く覚える事が、合格の近道です。
そして、記述問題対策としては、とにかく書くことが重要。より丁寧に、単語は正確に、漢字も覚えましょう。
テーマごとの回答例を、しっかりと準備しておきましょう。
語呂合わせの活用
試験対策としては、正確な数字の丸暗記が必須です。
実は、一次試験のために学んだ知識が活かせる問題が多いです。
ただし、文章の中の穴あきを埋める穴埋め問題形式が多い為、今まで以上に長く全体を覚える必要があります。
法規法令の確認も大事。
労働安全衛生法や建築基準法などは、改正される事があります。
このブログは2024年の法律を基にしていますから、最新の法規法令を常に確認し、正確な情報を得ることが重要。
各公式HPを定期的にチェックし、アップデートされた情報に注意を払うことが大切で、これは現場で活きる知識です。


コメントをお書きください