↑無料NOTEを書きました。読むと、やる気が出て暗記効率が上がりますから、試験勉強の合間に読むことをオススメします。

1級建築施工管理技術検定の覚え方と勉強法
このブログは2024年基準の情報をもとに、一級建築施工管理技術検定に出題される可能性がある問題の覚え方や、
法規法令や過去問の重要性を強調し、独自の見解を提供しますが、
※あくまでも暗記方法は試験対策用の説明として御理解ください。
過去に出題された問題や、出題が予測されるテーマを説明していきます。
もしも、同じ選択肢が出題されたらラッキーですし、言葉や数字をほんの少し変えた選択肢が、間違えの選択肢として出題される可能性もあります。
だからこそ、しっかりと数値と用語の組み合わせを暗記することが、合格への近道です。
今回のテーマ
【試験直前に詰め込む過去問】
今回は、試験直前ですので、さくっとガツッと、要注意な過去問たちを紹介します。
【過去ブログまとめ一覧】は、試験前に全て再確認することがオススメです。※文章クリックで移動します。
【質問文にも要注意!規定されているものを選ぶのか、間違えを選ぶのか、よく読むように!!】
・質問文例:日本産業規格(JIS)において、外壁面に用いる次の金属製建具における性能項目として、規定されているものはどれか。
・スライディングドアセット
【不正解】✘ねじり強さ
・スイングドアセット
【不正解】✘開閉繰り返し
・スライディングサッシ
【不正解】✘耐衝撃性
・スイングサッシ
【正解】鉛直荷重強さ
※※質問文をよーく読まないと、不正解の選択肢を見つけて、問題を回答してしまう可能性があります。
選択肢は4項目を全て読む、応用問題なら5項目、よーくよーく読みましょう。

あくまでも古い過去問の選択肢として覚えておきましょうという選択肢の紹介です。
これは全体を通して言えることですが、古い過去問や、問題文と選択肢のちょっとした言いまわしに要注意です。
そして試験では、過去の現場経験を基にした判断ではなく、試験問題として正確な知識を基に回答してください。
様々な現場状況、色々な材料がありますが、真実の答えはたった1つですから、よく文章を読んで見抜いて回答しましょう!
・質問文例:建築用シーリング材に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
【正解】1成分形高モジュラス形シリコーン系シーリング材は、耐熱性、耐寒性に優れ、防かび剤を添加したものは、浴槽や洗面化粧台などの水まわりの目地に用いられる。
【大間違いの不正解選択肢】✘シリコーン系シーリング材は、耐候性、耐久性に劣る。
【大間違いの不正解選択肢】✘シリコーン系シーリング材は、表面にほこりが付着しないため、目地周辺に撥水汚染が生じにくい。
【大間違いの不正解選択肢】✘成分形ポリウレタン系シーリング材は、耐熱性、耐候性に優れ、金属パネルや金属笠木などの目地に用いられる。
【正解】弾性シーリング材は、液状ポリマーを主成分としたもので、施工後は硬化し、ゴム状弾性を発現する。
【正解】シーリング材のクラスは、目地幅に対する拡大率及び縮小率で区分が設定されている。
【正解】弾性シーリング材とは、目地のムーブメントによって生じた応力がひずみにほぼ比例するシーリング材である。
【正解】塑性シーリング材とは、目地のムーブメントによって生じた応力がムーブメントの速度にほぼ比例し、ムーブメントが停止すると素早く緩和するシーリング材である。
【正解】日本産業規格(JIS)によるタイプFは、グレイジング以外の用途に使用するシーリング材である。
※日本産業規格(JIS)によるタイプGはグレイジング用(ガラス取り付け用)のシーリング材です。
【正解】2成分形シーリング材は、施工直前に基剤と硬化剤を調合し、練り混ぜて使用する。
※基剤と硬化剤 という、当たり前の組み合わせに注意しましょう。違う単語は不正解の可能性有り。
【不正解の選択肢】✘2成分形シーリング材は、空気中の水分や酸素と反応して表面から硬化する。
→正解の場合は、1成分形シーリング材は、空気中の水分や酸素と反応して表面から硬化する。です。
※一般的に、2成分とは、基剤と硬化剤を混ぜることで、化学反応により反応硬化するものだと覚えておきましょう。

・質問文例:労働基準法上、誤っているものはどれか。
【正解の選択肢】使用者は、満17才の男子労働者を交替制で午後10時以降に労働させることができる。
※一般的な解説として↓
原則として、労働基準法により、18歳未満の年少者は深夜業が禁止されています。
ただし、同条但し書きで、「交替制によって使用する満16歳以上の男性」は、深夜業が認められています。
一見すると不正解にも思える選択肢ですが、原則と例外的な内容をしっかり覚えておきましょう。

【不正解の選択肢】ステンレス鋼のSUS430は、SUS304に比べ磁性が弱い。
→正解の場合はステンレス鋼のSUS430は、SUS304に比べ磁性が強い。となります。
※覚え方としては、ステンレスは純度が高い方が磁性が弱いと覚えます。
純度が高い方が、名称の数字が低く(少なく)なります。
磁性が弱い、つまり純度が高い、優秀、2級より1級が高い評価、ナンバー2よりナンバー1が偉いというようなイメージでいきましょう。
名称の数字が少ない方が、混じり物が少ない、つまり純度が高い方が、磁性が弱く名称の数字は低い、そんな感じで覚えます。

・質問文例:仮設工事に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
【大間違い不正解の選択肢】高さ5mの作業構台の床材間のすき間は4cmとした。
→床材間のすき間は3cm以下とした。が、正解です。
3センチが正解です。
桟橋のようだから、さんばしで、さん、3が正解だと覚えてください。
4センチだと、4で、し、死を連想させるからダメ、NG、ブッブーだと覚えましょう。
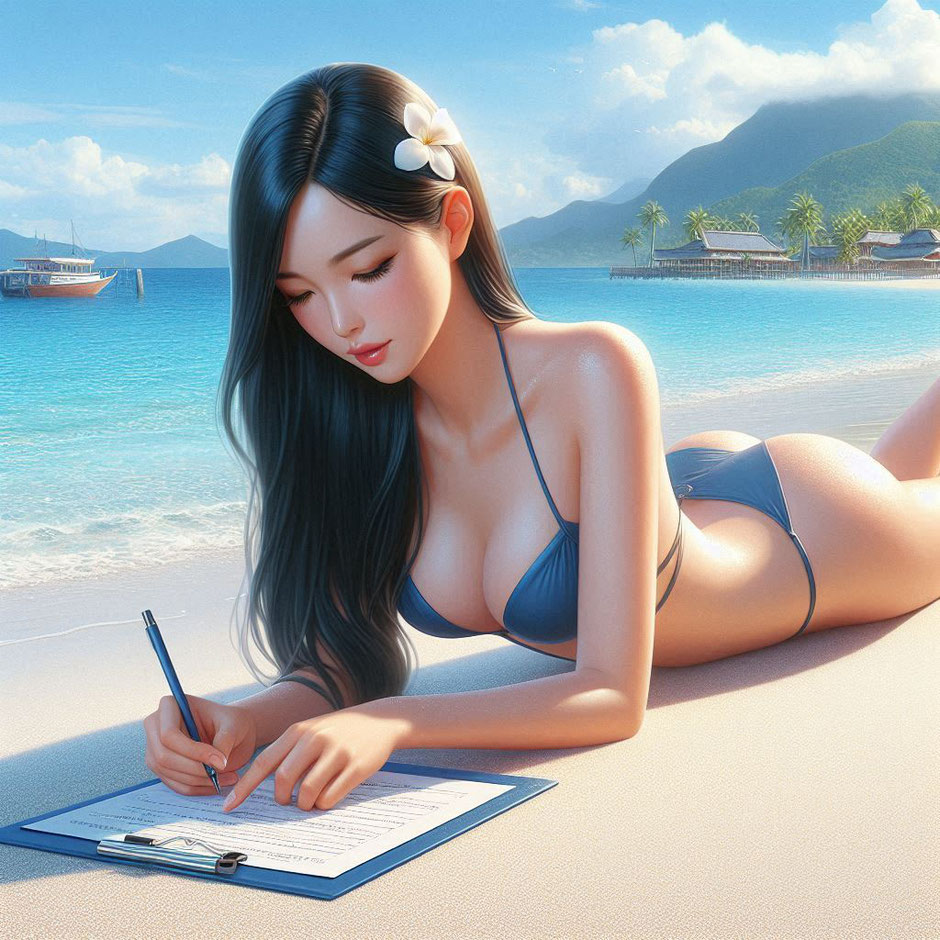
・質問文例:金属板葺屋根工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
【不正解の選択肢】平葺の吊子は、葺板と同種同厚の材とし、幅20mm、長さ50mmとした。
→正解は、平葺の吊子は幅30mm、長さ70mm。
覚え方は、サル(30)のようになれ(70)、サルのようが木にくっつくように、くっつけ、離れるな、そんな感じで覚えましょう。
屋根の金物というイメージで、屋根、高いところ、木、木登りと言えば、サル、という連想の記憶術です。

・質問文例:.次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれ
か。
【正解】回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測定する。
→覚え方は、30なので、30=み3る0、と読む。
あくまで暗記術として、階段をあがる美女がいたら、まあ狭い方の端から見るよね。見る、みる、30、端から30cmの位置において測定する。そんな感じで覚えます。

・質問文例:高層建築の鉄骨工事において、所要工期算出のための各作業の一般的な能率に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
【不正解の選択肢】補助クレーンを併用するため、タワークレーンの鉄骨建方作業のみに占める時間の割合を、30%とした。
→正解の場合は50~60%とした。が想定されます。
覚え方は、ゴルァとならないように、補助クレーンを併用しよう!
ゴルァ、ゴ5ル0ァ、と作業時間計画が合わないというか少なくて、ブチギレいる人を想像して覚えよう!!
50%より低いと、ゴルァって怒られちゃうからな、的なフィーリングです。

・質問文例:駆体工事の施工計画に関する記述として、最も不適なものはどれか。
【不正解の大間違い選択肢】✘鉄骨工事で、板厚6mmを超える鉄骨部材に仮設関係の取付け金物を手溶接で取り付ける場合、金物の溶接長さは20㎜とすることとした。
→一般的な正解例としては、40㎜程度です。20ミリは短すぎます。
※覚え方は、ムダなくムラなく素人にはできない溶接仕事。
ム6、で板厚6ミリを覚えて、素人、しろーと、し4ろーと(0)という感じで、40を覚えます。覚えられます。

・質問文例:安全管理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
【正解】墜落による危険を防止するためのネットは、原則として使用開始後1年以内及びその後6月以内ごとに1回、定期に試験用糸について等速引張試験を行わなければならない。
→覚え方は、ネット点検は無意味ではない。これで、む(6)い(1)みではない(1)、という感じで、さくっと丸暗記です。

・質問文例:仕上工事の施工計画に関する記述として、最も不適なものはどれか。
【不正解の選択肢】 石工事において、取付け終了後の大理石面の清掃にあたって、周辺の金物を十分養生したうえで酸
類を使用することとした。
→正解は、酸類は使用しないことにした。又は酸類は使用せず、酸類以外で清掃をした。
【過去問の正解選択肢】大理石は、酸には弱いが、緻密であり磨くと光沢が出るため、主に内装用として用いられる。
※覚え方、なんとなーく大理石って高級で強いみたいなイメージがありますが、所詮は石なので、酸性雨とかで溶けるイメージ、酸には弱いと覚えましょう。
石に比べて酸に強いタイルは、高温で加工してありますので酸に強いという理解で暗記です。
あとは、あくまでも暗記術として、水も滴るいい男とか、水もしたたるいい女とか言うことがありますから、
水、つまり、雨に濡れたいい女には弱い、意志が負けると、つまり、雨に濡れると意志がダメになると。
石のような意思も、雨にぬれた、水もしたたるいい女には弱いみたいな。
そんな感じで、酸性雨に石は弱いと暗記してください。
これは、そういう覚え方もありますよって話しです。

■材料保管については、似たような文章なので細部に注意しましょう。
【正解】床シート類は、屋内の乾燥した場所に、直射日光を避けて縦置きにして保管した。
【不正解の選択肢】✘ロール状に巻いたカーペットは、屋内の乾燥した場所に、縦置きにして保管した。
→俵積みで2〜3段程度が正解なので、横置きです。
※重いものは、縦置きすると危ないと覚える方法もありますし、床シート、内装、トイレ、トイレットペーパーと同じ縦置きで、
カーペットはフニャフニャで重いので、縦置きできませんと覚えましょう。
カーペットは、フニャフニャでたたないよーという暗記術です。

・質問文例:作業主任者の職務として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
【不正解】建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を作業計画として定めること。
→一般的に、事業主が定めることが正解です。
【不正解】木造建築物の組立て等作業主任者は、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
→不良品を取り除くことは、作業主任者の職務ではないですし、手配した元請けや事業主が点検してくれないと、そんなのもう、やってられないと覚えましょう。
【正解】木造建築物の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
【正解】土止め支保工作業主任者は、材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
【正解】足場の組立て等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
【正解】型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

・質問文例:仮設工事に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
【正解】移動はしごは、幅が30cmのものを用いた。
※覚え方は、サルのように登れる移動ハシゴ、さ3る0、で30、または両足の幅を合わせたら、だいたい30センチくらいかな、みたいなイメージです。
【正解】脚立を使用するときは、脚立の脚と水平面との角度を75度とした。
※覚え方は、角度は、斜めにこうだ!斜めにこう!みたいな感じで、な7なめにこ5う、で75度を覚えてください。
※あくまでも本ブログの内容は試験対策の暗記方法としての解説です。正確な詳細や用途は各公式HP等をご確認ください。

↑無料NOTEを書きました。読むと、やる気が出て暗記効率が上がりますから、試験勉強の合間に読むことをオススメします。

効率的な勉強法は、過去問を解き続けること。
過去問の重要性
とにかく出題範囲が広いため、本、アプリ、他のサイトでも、なんでもよいので過去問を解くことが最重要。
なぜなら、例年、過去問から選択肢が出題されていますから、正解の選択肢を多く覚える事が、合格の近道です。
そして、応用問題という足切りシステムを攻略するカギは、残念ながら、過去問を解き続けることしかありません。
語呂合わせの活用
試験対策としては、正確な数字の丸暗記が必須です。語呂合わせや覚えやすいフレーズをつかって覚えましょう。
いかにして、試験中にスムーズに思い出せるかどうかが、合否に大きく影響します。
ここの詰めが甘いと、本番で、ひっかけ問題にやられます。苦手な部分は、何度も何度も繰り返して学習しましょう。
法規法令の確認も大事。
労働安全衛生法や建築基準法などは、改正される事があります。
このブログは2024年の法律を基にしていますから、最新の法規法令を常に確認し、正確な情報を得ることが重要。
各公式HPを定期的にチェックし、アップデートされた情報に注意を払うことが大切で、これは現場で活きる知識です。

コメントをお書きください